中小企業のDXが進まない理由はコレだ! 最新の補助金活用の方法や成功事例までわかりやすく紹介。
「DX」という言葉を耳にする機会は増えましたが、実際に自社で進めようとすると「人材がいない」「資金が足りない」「何から始めればいいのかわからない」と悩む中小企業は多いのではないでしょうか。
DXは決して大企業だけのものではなく、小さな業務改善からでも始められます。
本記事では、中小企業でDXが進まない主な理由を整理し、補助金の活用方法や成功事例、そしてDX化を成功に導くための秘訣をわかりやすく紹介します。
目次
DX(ディーエックス)とは?
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、企業や組織がデジタル技術を活用して、様々な業務フローを刷新し、生産性を向上させる取り組みです。
おもに、情報をデータで管理するために、クラウドサービス、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などを導入します。これにより業務の効率化、顧客体験の向上、収益の増加など、さまざまなメリットがあります。
中小企業でのDX化の現状と課題
中小企業におけるDX化の現状は、大企業に比べると遅れがちです。しかし、DXは中小企業が市場で競争力を維持するために不可欠な要素と認識されており、取り組む必要性が高まっています。
DX化を図るには予算や人員といったリソースの制約だけでなく、企業のビジョンや戦略を明確化し社員全員が一丸となって取り組む状態を作ることや、ITの技術や知識の習得、そしてDXを推進するリーダーシップなど、様々な要件が必要です。いずれにせよ企業組織の変革にはそれなりのリソースと根気が必要ですが、将来に向けて少しでも速く取り組むことが推奨されています。
中小企業のDX化が進まない理由
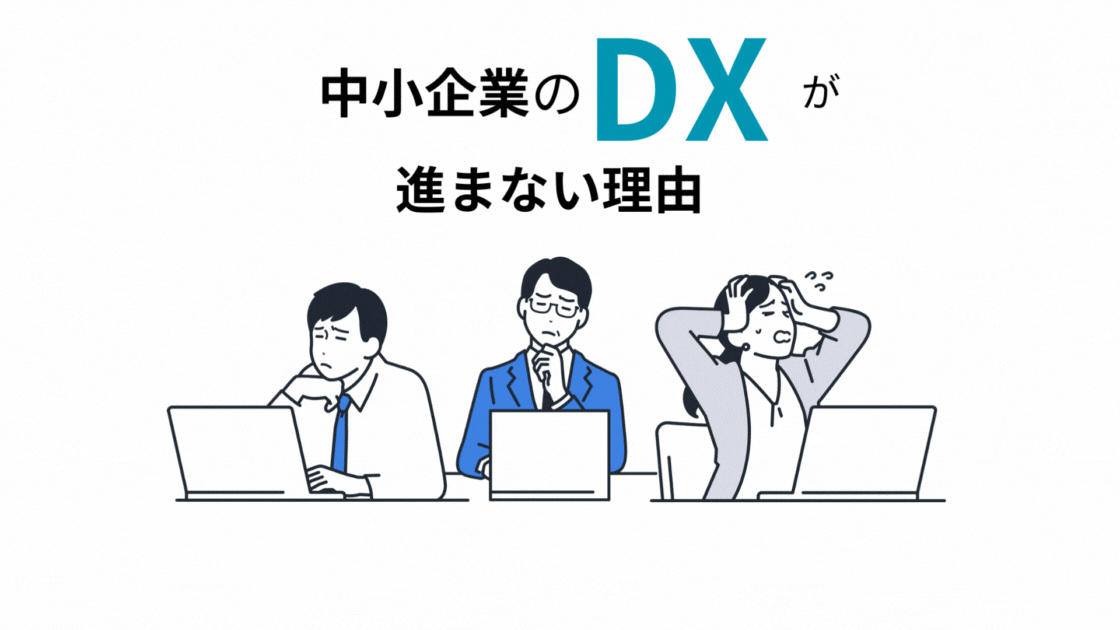
中小企業でDX化が進まない理由が一概に全ての中小企業に当てはまるわけではありませんが、以下にいくつか挙げてみます。
認識不足
まず経営者が「DX」という言葉の持つ意味を聞いたことはあっても詳しくは知らない、中小企業なので必要性を感じていないといった問題があります。
実際、令和5年3月に独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)によって行われた「中小企業のDX推進に関するアンケート」では、DX について理解している(「理解している」「ある程度理解している」)企業は約4割にとどまる結果となっています。
人材不足
さらに、いざDX化を進めたいと思っても、中小企業にはDXやITに詳しい人材がいないという現状が多いことがわかっています。
こちらも中小機構の「中小企業のDX推進に関するアンケート」の中で、「DX に取り組むに当たっての課題」の上位が「DX に関わる人材が足りない(31.1%)」、「IT に関わる人材が足りない(24.9%)」となっていることから、中小企業のDX化が進まない大きな原因となっています。
資金不足
人材の次に不足すると考えられているのが資金です。DX化を進めるためには、デジタル機器や社内のインターネット設備のアップデートが必要となることから、そうした資金を捻出できないと考える中小企業が多いです。
中小企業のDX化の必要性とメリット
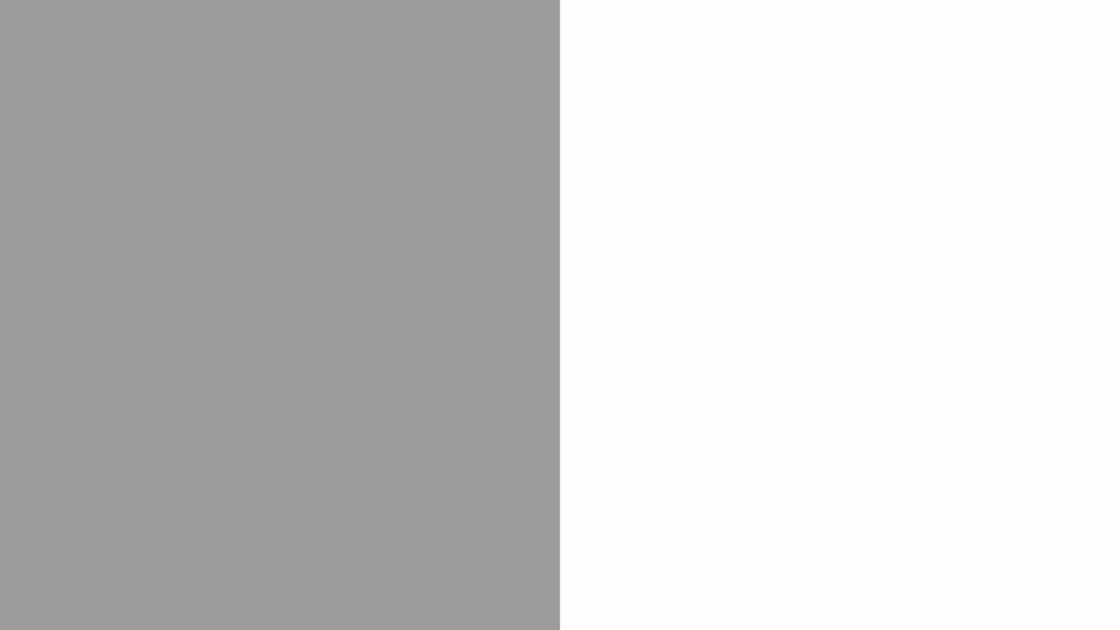
競争力の強化
DX化により、市場の変化やお客様の要望に素早く対応できるようになります。
さらに、デジタル技術を駆使してビジネスプロセスを効率化し、コストを削減することも可能です。それにより同業他社に負けない競争力を持ち続けることができます。
新たなビジネスアイデアの発掘
DX化を図ることで、これまでの業務工数を減らすことができるので、削減できた分のリソースを新しいビジネスやサービスの創出に利用することができます。これにより企業は新たな収益源を開拓できるチャンスが生まれ、市場でのニーズに合った革新的なソリューションを提供することで新規顧客の獲得が期待されます。
データドリブンな意思決定
DX化により、企業は大量のデータを収集し分析できるようになります。これにより、データドリブン(積極的なデータ活用により、意思決定や行動を促進するアプローチ)が可能となり、ビジネスの効果的な運営が可能になります。
また、クラウドサービスなどデジタルツールを活用することで、企業内での情報共有がリアルタイムで行えるようになり、スピーディな対応が実現できます。
中小企業のDX化の進め方
中小企業でDX化を進めるための具体的な方法を経済産業省の「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き(本体)」から見ていきます。
意思決定
将来どのような企業を目指すのか長期的なスパンで経営ビジョンを見据え、DX推進チームなどを設定します。
もちろん主導は経営者によるものでなければなりませんが、中小企業で経営者や役員だけでは技術的な課題解決が難しいという場合には、適宜外部のコンサルといった人材を登用することも必要となります。
全体構想・意識改革
意思決定で方向性が決まれば、あとは全社の意識改革です。中小企業の場合は逆に規模が小さいことから、全社でのDX化に取り組みやすいと言えるでしょう。全社員やスタッフにDX化の今後の方針や流れを理解してもらう必要があるため、身近な業務から徐々に取り組んでいくという流れが適しています。
推進
従来の業務プロセスを見直し改革を行っていきますが、それには全社の既存データ収集が大切なポイントになります。どの部分を見直してDX化を行えば業務効率化につながるのか、しっかり確認した上で進めていきます。
拡大
顧客ニーズに柔軟に対応できる状態を作ることがDXの醍醐味とも言えます。
DX化は一度行って終わりというものではなく、社会の変化に合わせて継続して行っていく取り組みになるため、ここからまた新たな意思決定につなげていくようにすることが望ましいです。
経済産業省のデジタルガバナンス・コードについて
経済産業省が提供している「中堅・中小企業向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」は、中堅・中小企業のDX推進を後押しするためのガイドです。どのようにDXを始めるか具体的にわからない方を対象にしており、全国各地でDXに取り組む企業の11の成功事例や、DXのステップ・バイ・ステップでの進め方をわかりやすく説明しています。
さらに、DXを成功させるための6つのポイントも示されています。
このガイドは、2020年11月に初版がまとめられ、その後2022年に「デジタルガバナンス・コード2.0」として改訂されました。またスタンダード版(原本)だけでなく、図表を中心にした”要約版”と、1枚の表と裏にまとめた簡潔な”概要版”の3つのバージョンが提供されています。
DXにおける経営者の役割
DXの推進と経営戦略の統合
経営者は、企業の長期的なビジョンに基づきDX戦略を策定し、これを経営戦略全体とすり合わせ統合する必要があります。DXにおけるビジョンを社内外に明確に伝え、理解と協力を得た上で実行するためのロードマップの作成が求められます。
組織文化の変革と人材の確保
従業員が新しいアイデアを自由に提案できる環境を整え、失敗を許容する文化を醸成することやマインドセット(固定概念や既存の価値観)の変革が必要です。
また、DXを推進するための人材を内部育成するか、外部から人材を採用をしたりコンサルティング企業やベンダーのサポートを仰ぎながら戦略を立てます。
リスク管理と投資決定
DX化に伴うリスクを想定した上で、必要な投資を行う意思決定が経営者にとって必要不可欠です。
また、DX戦略においては、定期的な評価や見直し限られたリソースを効率的に配分しDXの取り組みにおける投資の最適化を図ることが成功の鍵となります。
中小企業のDX化の成功事例
DX化は大企業がやることと考えている経営者も多い中、すでに取り組んでいる中小企業の事例を経済産業省の「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き(本体)」より抜粋して紹介します。
株式会社ヒバラコーポレーション(茨城県東海村)の取り組み

株式会社ヒバラコーポレーションは、1967年設立の工業塗装会社です。
まず人材不足を解決するために、業務を効率化させて今いる人材で対応できるようにスキャナーやプリンターを導入し、伝票などをデジタル化しました。
その後も技術のデータ化と生産管理のIT化により、継承が困難であった職人の技術を数値化し、本人以外の技能者が再現することを可能としています。
また、あらゆるデータを可視化することで、コストダウン、誤発注・誤入力の防止、管理に携わる時間の削減を達成してきました。
株式会社竹屋旅館(静岡県静岡市)の取り組み

静岡にある株式会社竹屋旅館では、人手不足や清掃業務委託費高騰という問題を解決するため、デジタル技術を使った清掃業務の内製化を行いました。業務を数値化して成果指標の設定を行うことで清掃時間を減らすことができ、結果として接客の質も上がり、お客様満足度(クチコミ)の評価点数も上昇しました。
また、宿泊客のアメニティグッズの消費具合をデータで可視化することでコスト削減を図っています。
東洋電装株式会社(広島県広島市)の取り組み

広島にある東洋電装株式会社は、制御盤製造及び技術サービス業を営む企業です。
まず小ロット品の生産性を上げるため、製造工程を分析して工程の標準化に取り組むことにしました。その際、社長をトップとするプロジェクトチームを設置し、職人の意見も聞きながらプロジェクトを進めました。
各作業をデジタル化しデータを収集・見える化することで、時間が掛かる作業を抽出・分析し、プロセス、人員配置、工程を最適に組み替えました。これにより作業時間の短縮やコストの削減が実現しています。
中小企業がDX化をするために利用できる補助金制度
DX化を進めたいと考えていても、「資金が足りない」「導入コストが不安」と感じる中小企業は少なくありません。そんな時に頼りになるのが、国や自治体が提供する補助金制度です。返済の必要がなく、条件を満たせば幅広い取り組みに活用できるため、DXの初期投資を大きく軽減できます。ここでは、利用できる代表的な補助金制度をご紹介します。
IT導入補助金
中小企業が最も利用しやすい補助金の一つです。会計ソフトや受発注システム、POSレジ、クラウドサービスの導入費用などが対象で、幅広い業務に対応できます。補助額は最大450万円、補助率は1/2から最大4/5と高く、初めてDXに取り組む企業に特におすすめです。
中小企業新事業進出補助金(旧・事業再構築補助金)
新市場への進出や高付加価値事業への挑戦を支援する制度です。DXを伴う新規事業の立ち上げにも活用でき、従業員規模に応じて最大9,000万円まで補助を受けられます。補助率は1/2で、成長を大きく加速させたい中小企業に適しています。
中小企業省力化投資補助金
人手不足を補うための設備投資を後押しする制度です。清掃ロボットや自動搬送システム、AIを活用した業務効率化ツールなどが対象となり、補助額は数百万円から1億円規模まで幅広いのが特徴です。人材不足に悩む企業が導入を進める際に効果的な補助金です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者を対象とした制度で、ホームページ制作やECサイト構築、クラウドシステムの導入などに活用できます。補助上限は50万円から200万円程度、補助率は2/3で、比較的申請のハードルが低く、初めて補助金を使う事業者にも適しています。
自治体独自のDX支援制度
国の制度だけでなく、各自治体でも独自のDX支援が行われています。例えば東京都では「中小企業DX推進助成金」、大阪府では「DXモデル創出促進事業」などがあり、最大300万〜500万円規模の助成を受けられる場合もあります。地域により内容は異なるため、必ず自社の所在する自治体の最新情報を確認することが大切です。
東京都の例:[東京都中小企業振興公社 DX推進助成金]
大阪府の例:[大阪府 DXモデル創出促進事業]
導入失敗事例とその教訓
中小企業が一斉にDX化に取り組んでいる中で、当然ながら成功しなかった事例や課題を抱える企業も存在します。
ここでは、具体的なケースとその背後にある要因、そしてそこから得られる教訓について説明します。
事例1:レガシーシステムからの脱却を急いだ小売店

家具小売店のA社は、長い間、在庫管理や販売管理に紙ベースの手法を採用してきました。しかし、競合他社がデジタル化に成功し、世の中ではオンラインショッピングの需要が高まったことから、A社も急ピッチでDXに取り組みました。
失敗の要因
- スピード優先の選択
A社はDX化を急いで進め、新しいPOSシステムを導入しましたが、従業員に十分なトレーニングを提供しないままシステムを稼働させてしまったがために、業務フローが煩雑となり、ミスが増加し、かえって悪影響を及ぼすことになりました。
- 無計画なWeb広告
急いでGoogleやSNS広告など複数の広告運用を行ったことで、的確な戦略が欠けていたことで思うような成果が得られませんでした。結果として広告費が無駄になり、期待通りの成果が得られない状況となりました。
教訓
DX化プロジェクトにおいて、計画立案と適切なトレーニングは不可欠です。スピードは大切ですが無計画な取り組みは逆効果になりかねません。同様に、Web広告も戦略的な計画を立て、投資対効果を考慮した運用が必要です。
事例2:複雑なシステム導入による医療機関の混乱

B診療所は、患者の情報管理を向上させるために、新しい電子健康記録(EHR・電子カルテ)システムの導入を決定しました。
しかし、この新しいシステムは非常に複雑かつ包括的であり、看護スタッフを含む全ての従業員に対するトレーニングと導入に多くの時間とリソースを要しました。
失敗の要因
- 過度な複雑性
新しいEHRシステムは非常に高度な機能を備えており、医療スタッフはそれを理解するのに時間がかかりました。システムの操作が難しいためエラーが頻発し、データが錯綜する結果となりました。
- 適切なトレーニング不足
スタッフへのトレーニングも不十分であり、システムの適切な利用・運用をトレーニングする時間の確保や、レクチャーできる人材の準備が不十分だったことが要因でした。
教訓
DXプロジェクトにおいて、システムの複雑さに対するトレーニングの重要性は見過ごされがちです。こうした問題を回避するために、最初はシンプルな機能から導入を開始し、従業員の適切なトレーニングに重点を置くことが成功の鍵となります。
事例3:早すぎたスマート工場の導入による生産停止
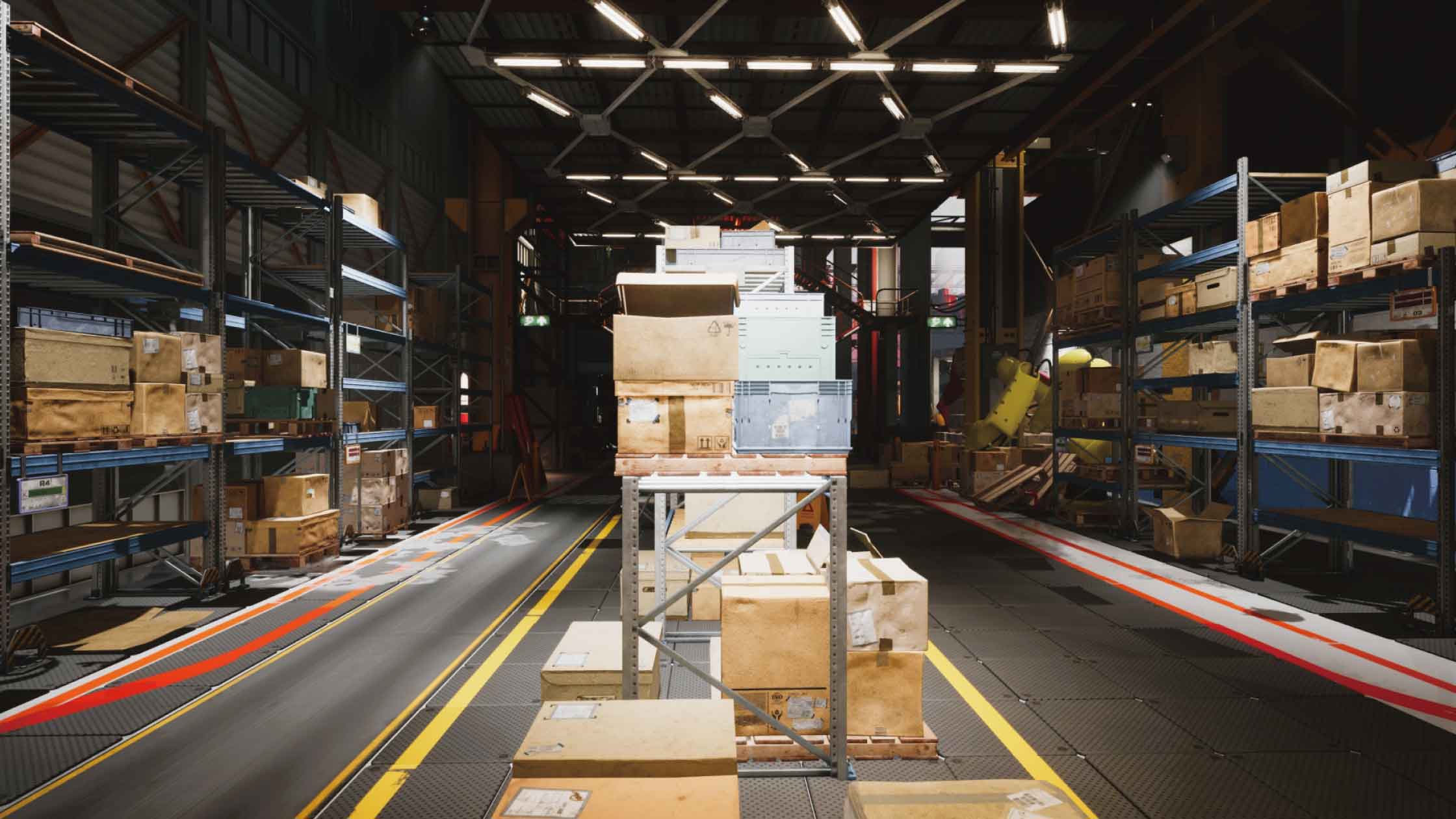
C工業では、スマート工場(スマートファクトリー)の導入を決定しました。
工場内の各種設備をネットワークで接続し、センサー技術とIoTデバイスを活用して生産ラインを効率化し、不良品も事前に検出することを目標にしました。
失敗の要因
- 不十分なテスト
導入前のテストとデバッグが不足しており、事前のシミュレーションが充分ではありませんでした。
その結果、生産ラインが意図しない停止を何度も経験し、製品供給に支障が生じました。
- 従業員への準備不足
システム操作に必要なトレーニングとガイダンスが従業員に浸透しておらず、新しいシステムへの適応が困難でした。
また、事前のテストも十分に実施されておらず、準備不足であったことが要因となりました。
教訓
新しいテクノロジーを導入する際には、綿密なテストとトレーニングが欠かせません。
従業員の関与と準備は成功に不可欠な要素です。
早すぎるシステム導入は問題を引き起こす可能性が高いため、慎重なシステムの移行計画が必須です。
中小企業のDX化ソリューションにはクラウドERPシステム「キャムマックス」がおすすめ

中小企業がDXを実現するうえで大きな壁となるのが、「人手不足」と「コストの制約」です。そこで注目されているのが、クラウドERPシステム「キャムマックス」です。クラウド型なので初期費用を抑えつつ、導入後すぐに業務を効率化できる点が特徴です。
「キャムマックス」では、生産管理・販売管理・在庫管理・会計管理といった中小企業の基幹業務をひとつにまとめ、部門ごとにバラバラだった情報を一元管理できます。これにより、受発注や在庫の状況、売上や利益の把握までをリアルタイムで確認できるため、経営判断のスピードと精度が格段に向上します。また、クラウド型のため社内に専用サーバーを置く必要がなく、インターネット環境さえあれば在宅勤務や出張先からも利用可能です。
さらに、導入コストが明確でわかりやすいのも魅力です。月額9万円から利用でき、最大5人まで同時利用が可能。小規模チームでも無理なく導入でき、事業の成長に合わせて柔軟に拡張できる点が中小企業にとって安心です。加えて、ECモールや会計ソフト、倉庫管理システム(WMS)など外部サービスとのAPI連携も充実しているため、業務全体をシームレスにつなぐことが可能です。
このように「キャムマックス」は、低コストで導入しやすく、必要な機能を網羅しつつ成長に合わせて拡張できるクラウドERPシステムです。DX化を検討している中小企業にとって、最初の一歩を踏み出すうえで非常に頼れるソリューションといえるでしょう。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。
