EDIとは? Web-EDIの違いや仕組み、導入メリットをわかりやすく解説
企業間の取引では、見積書や発注書などの帳票類が欠かせません。
しかし、取引先ごとにフォーマットが異なることで、業務負担が増え、効率化の妨げになるケースも少なくありません。こうした課題を解決する手段として注目されているのがEDI(電子データ交換)です。特に近年では、インターネットを活用した「Web-EDI」の導入が進んでおり、低コストかつ導入しやすい選択肢として多くの企業が採用を始めています。
本記事では、EDIの基本からWeb-EDIとの違いや仕組み、そして導入によるメリット・デメリットまで、わかりやすく丁寧に解説します。
目次
EDIとは?

EDIとは、Electronic Data Interchangeの頭文字を取ったもので、日本語では「電子データ交換」とよばれます。
具体的には、プロトコルに基づいて注文書や請求書などのビジネス文書を電子化したものを、専用回線などを利用してやり取りすることをいい、特に企業間取引における受発注に関する書類データの交換を指します。
さらに、これを実現するシステムを指して単に「EDI」と呼ぶケースも多いです。
日本においては、2024年初頭にISDNサービス(INSネット/ディジタル通信モード)が終了の予定となっており、今後、次世代EDIへの移行が求められることになります。
EDIの基本概念と仕組み
EDIの基本概念
EDIは、企業間でのビジネス文書のやり取りを電子化し標準化することで、業務プロセスの合理化や効率化を図ることを目的としています。
また、ビジネス文書を電子的にやりとりするための規格や手順があり、EDIで使用される規格には国際的に認められた規格であるEDIFACTや日本独自の規格であるJEDIがあります。
そして、EDIの利用には専用のソフトウェアや通信回線が必要になります。
相手企業とのやり取りにあたっては、共通の規格や手順を確認し適切なセキュリティ対策を行うなど準備が必要となるため、EDIの導入には一定のコストや手間がかかります。
EDIの仕組み
EDIの仕組みは、企業間でやりとりされるビジネス文書を電子的にやり取りすることで、紙ベースで行われる手作業の作業時間やコストを削減し、正確性や迅速性を高めることができます。具体的には、注文書や請求書、配送伝票などさまざまなビジネス文書をEDIで電子化し、企業間でのやりとりを可能にします。ただし、導入にあたっては適切なセキュリティ対策が必要であり、専用のシステムや通信回線を整備する必要があります。
また、EDIとは別にWeb-EDIというものがあり、こちらはインターネット回線を利用して手軽に導入できるため、中小企業などでは積極的に利用されています。
EDI取引の具体例
業界別にEDIは多数存在しており、製薬メーカーが使う「JD-NETシステム」や、菓子業界のEDI「e-お菓子ねっと」、Amazon専用のEDIシステム「amazingEDI」、自動車部品メーカー間の部品調達に使われる「トヨタWG共通EDI」などがあります。
発注プロセス
小売業者(発注側)が必要な商品データを自社のシステムから選び、EDIを通じて供給業者(受注側)へ発注します。この際、双方が共通のデータ形式を用いることで、発注情報が即座に供給業者の受注システムに反映されます。
納品プロセス
供給業者は受け取った発注データに基づき商品を準備し、納品書をEDIで小売業者に送信します。納品書には、納品される商品の詳細情報や数量が記載されています。
請求・支払プロセス
商品納品後、供給業者は請求書をEDIを通じて小売業者に送信します。小売業者は請求書データを自社の会計システムで処理し、支払いを行います。
EDIと受発注管理システムの違い
EDIは企業間の取引におけるデータ交換の標準化と自動化に特化しているのに対し、受発注管理システムは企業内の業務効率化に焦点を当て、より幅広い機能を提供しています。両者は異なるニーズに対応するために設計されており、多くの場合、補完的に利用されます。
EDIの運用範囲
EDIは企業間(B2B)での文書やデータの電子的な交換を指します。このシステムを通じて、注文書、請求書、納品書などの商取引に関連する文書が標準化された形式でやり取りされます。特に大量の取引データを頻繁にやり取りするB2B取引において、効率性とスピードの向上に寄与します。
受発注管理システムの運用範囲
受発注管理システムは、外部企業とのデータ交換というよりも、在庫管理、納品管理などを含め、社内の業務フローの効率化に焦点を当てています。内部プロセスにおける自動化により業務効率は向上しますが、EDIのようにデータ交換自体のスピードを根本から大きく変えるわけではありません。
EDIの種類
現在のEDIには、利用されるコードやフォーマットの定め方で分けると、大きく「個別EDI」「標準EDI」「業界VAN」の3種類があります。
個別EDI
個別EDIとは、取引先ごとにコードやフォーマットを決めるタイプのEDIです。複数の取引先でルールを使い回せないため効率は悪いものの、個々に設定するため自由度が高い点はメリットです。また、発注者主導となりやすい傾向があり、受注者側で設定の負担が大きくなる可能性もあります。取引先数が少ない場合に適しています。
標準EDI
取引規約や運用ルール、フォーマット、データ交換形式を標準化したものが標準EDIです(コードの標準化は含みません)。
同じ規格を複数の取引先に適用できるため効率が良く、取引先を拡大しやすいのがメリットです。個別EDIのように発注者主導に傾かないため、受注者側の負担も軽減されます。
代表的なものに、「流通BMS」「中小企業EDI」があります。
業界VAN
標準EDIの中には、特定の業界に特化したネットワークサービスがあり、これを業界VANといいます。標準EDIでは、コードの標準化は行われていませんが、業界VANでは取引先コードや商品コードを特定業界に仕様に標準化しています。
日用品業界VANの「プラネット」、家庭用品・食品軽包装業界VANの「ハウネット」などがあります。
EDIのメリット

EDIを活用するメリットは何でしょうか?
主に「書類送付の自動化」「業務効率の向上」「データ入力の正確性向上」「ペーパーレスによる経費削減」の4つのメリットが挙げられます。
書類送付の自動化
EDIがない場合、注文書や請求書といった書類を郵送やFAX、メール添付などの手段を用いて手動で送付する必要があります。さらに、受け取った受注者側で届いた書類を元にデータ入力をし直さなければなりません。
一方、EDIで設定しておけば、送付を自動化でき、手間や人為ミスの低減が可能です。
業務効率の向上
前項でお伝えしたように、書類送付を自動化することで、業務の削減や人為ミスの低減を実現できます。
また、EDI の一機能であるEOSを活用できるため、在庫が調整されて在庫不足や過剰在庫が起きにくくなります。このため、在庫管理にかかる業務も削減でき、業務効率の向上につながります。
EOSについては「EDIとEOSの違い」をご覧ください。
データの正確性向上
EDIを活用すれば、発注者が入力したデータがそのまま受注者へ送信されるため、受注側でのデータ入力の手間が省けます。このため、入力ミスが起きにくくなり、データの正確性も向上できます。
また、受注側で故意にデータを改ざんすることもできなくなるため、内部統制の強化にも役立ちます。
ペーパーレスによる経費削減
「書類送付の自動化」でもお伝えした通り、EDIを活用すれば、注文書や請求書を印刷して郵送したりFAXを送ったりする必要がなくなります。このため、ペーパーレス化を実現でき、郵送費をはじめ、印刷のためのハードウェアや紙代、インク代、外注費などを削減することが可能です。
EDIのデメリット
EDIにはメリットが多い一方、デメリットがないわけではありません。
それが、自社と取引先で互換性のあるEDIを導入する必要があるという点です。
自社と取引先で互換性のあるEDIを導入する必要がある
EDIを活用するには、発注者側と受注者側の双方で互換性のあるEDIシステムを導入している必要があります。
たとえ自社がEDIを導入していても、取引先がEDIを導入していなければEDIを通して、注文書や請求書をやり取りすることはできません。互換性のないEDIが使われている場合も同様です。
EDIが未導入の取引先に対しては、引き続き、書面によるやり取りが発生する点は、EDIのデメリットといえるでしょう。
Web-EDIとは?
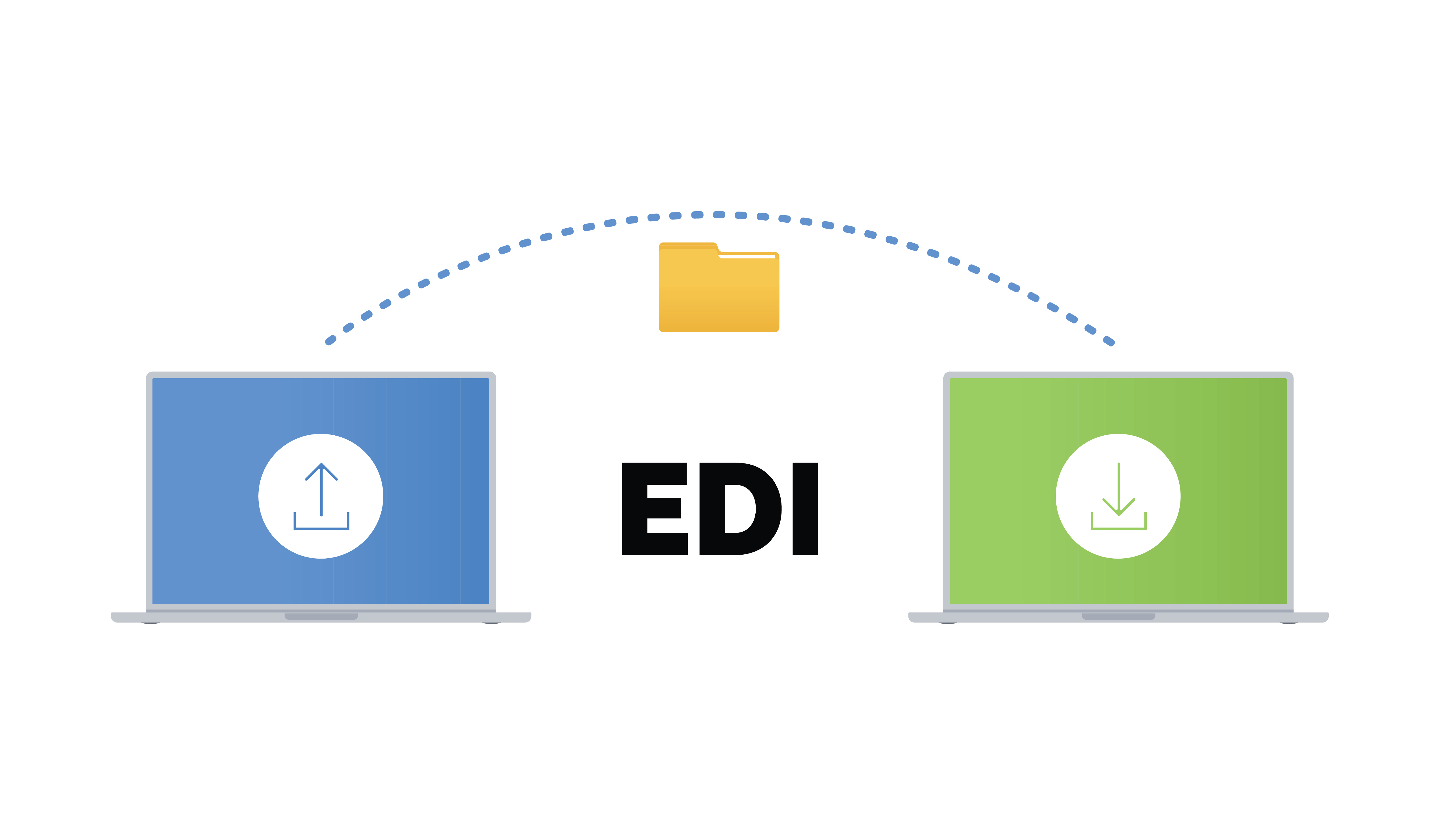
EDIの中で、近年、注目を集めているのが「Web-EDI」です。
Web-EDIは、企業間で取引するためのEDI(電子データ交換)の一種であり、Webブラウザを利用してインターネット上で注文書や請求書などがのやりとりが可能なシステムです。
従来のEDIとは違い、導入に必要な通信回線やソフトウェアを準備しなくても導入ができるため導入費用が安くなり、特に中小企業にとって利用しやすいシステムとして注目されています。
EDIとWeb-EDIの違い
「EDIの種類」では、利用されるコードやフォーマットを定めた規格で分けましたが、利用される通信回線によって分けると「レガシーEDI」と「インターネットEDI」に分けられます。
レガシーEDIとは、固定電話回線を利用して通信を行う、従来のEDIです。
「EDI2024年問題とは」でご紹介したように、固定電話回線は2024年初頭で終了が予定されています。今後は、次世代EDIへ移行しなければなりません。
一方、インターネットEDIとは、JX手順やebXML、MS、FTP、HTTPSといった通信プロトコルを用いてインターネットを利用して通信を行うEDIのことです。
Web-EDIは、このインターネットEDIの一つで、Webブラウザ上で利用でき、EDI 2024年問題を解決できるとして注目されています。
ただ、Web-EDIはまだ標準化されていないため、取引先とデータ変換の互換性などを調整する必要がある点には注意が必要です。
EDIとWeb-EDIのそれぞれのメリット・デメリット
EDI
EDIのメリットは、高速かつ確実なデータのやりとりができることです。また、データのフォーマットが統一されているため、データの受け渡しがスムーズに行えるという利点があります。ただし、専用回線を使用するため、導入コストが非常に高くなるという欠点があります。
Web-EDI
Web-EDIのメリットは、インターネット回線を使用するため、専用回線を引く必要がなく低コストで導入が可能であるという点です。
また、Webブラウザを使用してデータのやりとりができるため、専門知識がなくても容易に操作ができるという利点があります。しかし、インターネット回線を使用するため、通信速度が低下する場合があり、セキュリティの確保が必要であるという欠点があります。
Web-EDIの特徴
Web-EDIには、「ブラウザ上で操作可能」「クラウドでの提供」という2つの特徴があります。
ブラウザ上で操作可能
Web-EDIは、ブラウザ上で利用できるEDIです。
そのため、利用にはインターネット環境が必要ですが、逆に言えばインターネット環境さえあれば、スマートフォンなどからもアクセスできるため、利用する場所が限定されません。デスクトップパソコンを設置できないような場所でもEDIを利用することができます。また、通信手段としてインターネットを利用することで、従来の固定電話回線に比べると通信速度も格段に向上しています。
クラウドでの提供
Web-EDIの多くは、クラウドサービスとして提供されています。
このため、従来のようにEDIシステムをPCなどにインストールする必要はなく、アップデートなどのメンテンスも必要ありません。また、データの保存が分散されているため、データ消失のリスクが低減されます。
Web-EDIのメリットを詳しく解説
Web-EDIの最大のメリットは、主に「低コストでの導入・運用が可能」「導入までが早い」「セキュリティの向上」の3点です。また、取引先との情報共有を迅速かつ正確に行うことができる点です。
改めて、Web-EDIのメリットを整理してご紹介いたします。
低コストでの導入・運用が可能
従来のEDIは初期費用が高く、導入後のメンテンスも自社で行わなければならなかったため、運用コストもかかってきます。
一方、Web-EDIの場合は多くがクラウドサービスとして提供されるため、オンプレミス型のクラウドでない限りは初期費用を低く抑えられます。月額料金などのランニングコストはかかりますが、リーズナブルな料金体系のものが大半で、自社でメンテンスをしなくて済むことを考えると総じてコストは低いといえるでしょう。
導入までが早い
Web-EDIの多くはクラウドで提供されます。特にSaaS型であれば、導入のスピードは圧倒的に早く、従来のEDIのようにインストールや設定のために多くの時間を割く必要がありません。
セキュリティの担保
従来のEDIの多くでは通信に専用線が使われていたため、セキュアな環境で運用できました。
これに比べると、インターネット回線はサイバー攻撃も多く、情報セキュリティの観点で不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、近年の暗号化通信技術の向上はめざましいものがあります。また、Web-EDIの多くはクラウドで提供されており、ベースとなるAWSなどのクラウドサービスにおいても高いコストをかけてセキュリティ対策に注力しています。
以上の点から、専用線に比べてもセキュリティ面で遜色ないといえるでしょう。
Web-EDIの費用
Web-EDIには多くの製品があります。
大きく2種類にわかれており、自社内のサーバーでシステムを運用する形態オンプレミス型とはネットワークを通じてシステムにアクセスができるクラウド型です。
オンプレミス型
オンプレミス型の場合、導入費用はサーバーやハードウェア、ソフトウェアの購入費用が必要となり、また、運用費用としてサーバーのメンテナンス費用や保守費用が必要となりコストが気になる部分です。
クラウド型
クラウド型の場合は、導入費用が比較的安価で、利用料金が必要となるため、利用状況に応じて柔軟に費用を抑えることができます。自社にとってどちらがあっているのかを社内で方針を決めた上で製品を選びましょう。
Web-EDIの導入における注意点
Web-EDI導入時には、以下の問題点が考えられます。
- システム導入にかかる費用が発生する
- システムの使い方に慣れるまで時間がかかる
- 取引先がWeb-EDIに対応していない場合、手動でデータ入力をする必要がある
これらの問題点を解決するためには、他のシステムと同様で導入前にシステムの選定や取引先との調整、システム利用者の教育・訓練などをしっかりと行う必要があります。
またそれ以外にも注意点がありますのでご紹介していきます。
Web-EDIのセキュリティ対策
Web-EDIは、機密性の高い取引情報をインターネット上でやりとりするため、セキュリティ対策が非常に重要です。以下の対策が必要です。
- SSL/TLSなどの暗号化通信の導入
- アクセス制限やパスワード管理などのアクセス管理の強化
- ウイルスや不正アクセスに対する防御策の実施
- 適切なバックアップの取得
これらの対策を十分に実施することで、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
Web-EDIを活用したビジネスの生産性向上法
Web-EDIを導入することで、中小企業はさまざまな生産性向上のメリットを得ることができます。
以下では、取引先管理の効率化、データ分析による個別対応の強化、業界の統一化によるビジネスの向上のそれぞれについて説明します。
取引先管理の効率化方法
取引先ごとに用意していた専門端末や用紙が不要となり、伝票をデータで一元的に管理できます。
これにより、取引先管理の効率化が図れます。例えば、クライアントの注文履歴をデータ化することで以前の受注内容をすばやく確認でき、受注内容を間違えることを防ぐことができます。
データ分析による個別対応の強化
Web-EDIを活用することで、大量の受注・発注データを蓄積できます。
このデータを活用することで、クライアントごとに特化した受発注のデータを分析することができます。
例えば、クライアントが頻繁に注文する商品や納期が早いクライアントを特定することができます。このような情報を基により顧客に特化したサービスを提供することができ、顧客からの信頼感を高めることができます。
業界の統一化によるビジネスの向上
Web-EDIを業界全体で統一することで、以下のような効果が期待できます。
ビジネスの効率化
業界全体でWeb-EDIを統一することで、データの標準化が実現されます。そのため、取引先間でのデータのやり取りがスムーズに行えるようになりビジネスの効率化が進みます。
具体的には、例業界全体でのWeb-EDIの普及により月間1,000件以上の受発注を完全に電子化し、業務の効率化に成功したという例もあります。
業務コストの削減
データの標準化によって、データ変換にかかる時間やコストを削減できます。また、取引先とのやりとりが電子化されることで紙ベースの書類や電話・メールなどによるやりとりが不要になり、それに伴うコストも削減できます。
情報の可視化・分析化
業界全体でWeb-EDIを統一することで、データの可視化・分析化が容易になります。取引先や業界全体の動向を把握することができ、より的確なビジネス戦略の立案につながります。取引先の受注状況や販売動向をリアルタイムで把握し、迅速な対応が可能となります。
以上が、Web-EDIを導入した中小企業の目線での生産性向上や業界の統一化によるビジネスの向上についての具体的な効果です。
Web-EDIは中小企業でも手軽に導入することができ、ビジネスの効率化やコスト削減、情報の可視化・分析化など多くのメリットがあります。
Web-EDI対応の「キャムマックス」ならすぐに導入でき発注業務がスムーズに!

最後に、当社が提供する中小企業向けのクラウドERP「キャムマックス」について紹介させてください。
EDIのデータは、単独でも受発注や在庫管理の最適化に貢献しますが、売上や人件費などほかのデータと組み合わせて活用することで、経営課題の解決にも役立ちます。
そして、EDIデータをERPへ取り込む際に重要なのが「EDIマッピング」です。
EDIマッピング
取引先から受信したEDIデータをERPや他システムへ取り込む際には、データを変換する処理が必要になります。このデータ変換処理のルールを作成するのが「EDIマッピング」です。
仮に、ERPなど基幹システム側にマッピング機能がない場合には、仕様通りにExcelなどへ手作業で加工し、ERPなどのシステムに取り込むという手順になります。1社分だけでも大変な作業ですが、これを取引先ごとに対応するとなると面倒極まりなく、ミスによる手戻りが頻発する恐れがあります。
一方、マッピング機能があれば、データ処理の変換業務を大幅に効率化できます。ただ、マッピング機能は、単体のサービスとして用意されていることが多く、利用には別途、費用が発生します。
「キャムマックス」なら、標準機能としてマッピング機能が搭載されているため、EDIを利用している企業様に適したERPだといえます。
発注Web-EDI
「キャムマックス」には、EDIマッピングのほかに、仕入先にWeb-EDIを利用してもらえる「発注Web-EDI」の機能も搭載されています。
EDI未導入の取引先に対して、電話やFAX、郵送などで帳票をやり取りしているケースでも、自社が「キャムマックス」を導入することにより、取引先でも「発注Web-EDI」を利用してもらえ、販売・仕入を含めた取引を電子化できます。
連携できる機能
「キャムマックス」では、ティービー株式会社が開発・提供するクラウド帳票ツール「LinkPrint CLOUD(以下、LPC)」と連携しており、キャムマックスからLPCに直接データを受け渡し、LPCで必要なデータ項目を取捨選択して自由にレイアウトできます。
このほか、「キャムマックス」が連携している機能として、下記があります。
セキュリティについて
「キャムマックス」は、世界最高水準のセキュリティを誇るAmazon Web Servicesの環境下で稼働するため、情報セキュリティ面にも安心してご利用いただけます。
また、クラウドサービスでありながら、企業とデータベースは1対1対応のシングルテナントを採用しております。データの混在や情報漏えいの心配もありません。さらに、不正アクセス防止のため、WAF(WEBアプリケーションファイヤーウォール)を標準完備。ファイアウォールやIPS(侵入防止システム)で防ぎきれない外部の脅威からお客様の大切なデータを保護します。
サポート体制について
「キャムマックス」では、導入前、導入後問わず専任の担当者がサポートさせていただきます。
操作方法や機能についての不明点はもちろん、オプションの申込、ライセンス追加なども簡単にできます。また、会員様専用のコミュニティサイトも準備しており万全の体制でサポートさせていただきます。
EDIを活用し、DX化へ
EDIを活用することで、業務の効率化やデータの正確性、内部統制の強化などを実現できます。
未導入の企業様はもちろん、すでにEDIを活用していても、それがレガシーEDIである場合は、2024年のISDNサービス終了までに次世代EDIへの切り替えが必要なため、新たなEDIを選定することをおすすめします。
電子帳簿保存法の改正もあり、ペーパーレス化を一気に進めるチャンスです。
EDIを活用する際は、データを幅広く活用するためにも、ERPなど基幹システムとの連携が重要になってきます。
「キャムマックス」なら、EDIからのデータ変換処理を効率化する「EDIマッピング」を、標準機能としてご用意しておりますので、EDIの導入や切り替えのタイミングでERPも導入・切り替えしたいとお考えの企業様は、ぜひ詳細ページをご覧ください。
よくある質問
EDIとEOSの違い
EDIの仕組みの一部に「EOS」があります。EOSとは、Electronic Ordering Systemの頭文字を取ったもので、日本語では「電子受発注システム」とよばれます。
小売業や卸売業において、1970年代から主に在庫の適正化を目的として発注や仕入、請求、支払などの情報をやり取りに活用されてきました。
社外の仕入先とのデータのやり取りの際にEDIが必要となるため、現在は、EDIの一部として機能しています。EDIはこのほか、店舗と本部のやり取りにも利用されます。
EDI2024年問題とは
「EDIとは?」でも軽く触れましたが、ISDNサービス(INSネット/ディジタル通信モード)は、2024年の初頭でサービスを終了する予定となっています。
この背景には、将来的に固定電話の利用増が見込めないことが挙げられます。モバイル通信の契約数が右肩上がりで増加しているのに対し、固定電話の加入契約数が減少の一途をたどっており、IP電話については総数が2013年に固定電話を上回りました。このことから、NTTは固定電話の通信網をIP網に移行することを決めました。
もう一つの背景として、2025年には固定電話回線などを提供するために利用されてきた、公衆交換電話網(PSTN)の電話交換機の耐用年数が限界を迎えることもあります。
要するに、PSTNをマイグレーションするということなのですが、この対象になったのが加入電話とISDNサービス(INSネット/ディジタル通信モード)なのです。
そして、ISDNサービスはEDIの通信にも利用されています。2024年までに、次世代EDIに切り替える必要があります。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。



