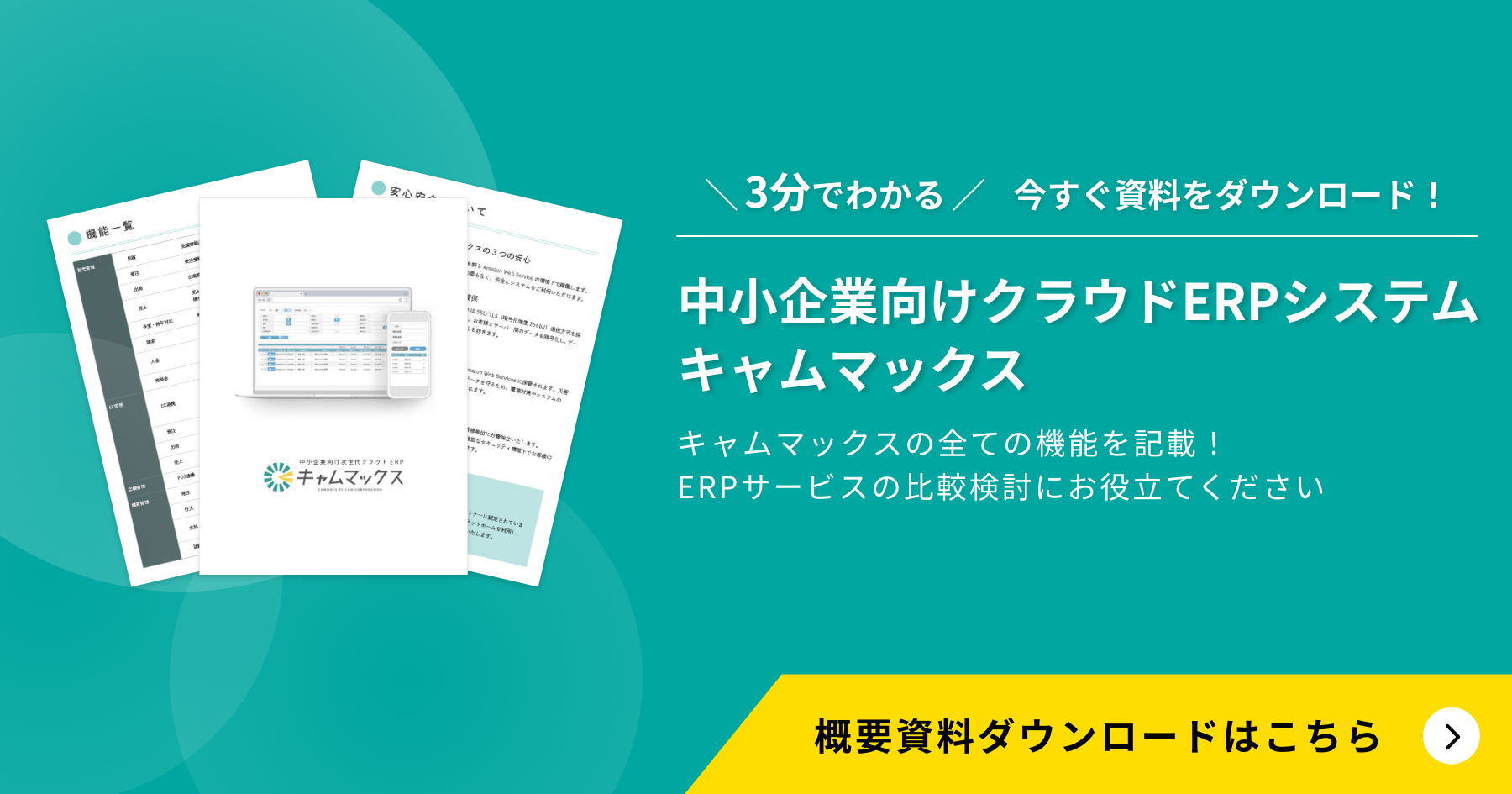インボイス制度とは?2023年10月からの新制度に向けて
インボイス制度とは2023年10月から始まる適格請求書等保存方式を使用する制度のことです。
現行の区分記載請求書にある記載事項に加えて適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率を記載した適格請求書(インボイス)を使用します。インボイス制度開始に伴う影響やすべきことをまとめました。
目次
インボイス制度とは?簡単にわかりやすく解説
インボイス制度とは「仕入税額控除」を受けるための新しい制度です。
具体的には、商品やサービスの取引時に、消費税の金額を明確に示す請求書(インボイスまたは適格請求書と呼ばれます)を作成・保存し、消費税の計算や申告に利用します。
この制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。
消費税を控除できる「仕入税額控除」とは
仕入税額控除とは、事業者が商品やサービスを仕入れる際に支払った消費税を、自身が商品やサービスを売った際に受け取る消費税から差し引く制度です。
つまり、事業者は自分が支払った消費税の一部を「控除」できることになります。
これにより、事業者の負担が軽減されていましたがインボイス制度では、この仕入税額控除を行うためには適格請求書の発行と保存が必要となります。
インボイス制度導入の目的と開始する理由
インボイス制度の導入には、消費税の計算をより正確にして税の公平性を高めることが目的とされています。
具体的には、事業者が商品やサービスを売った際の消費税とそれらを仕入れる際の消費税の間で、適切な控除が行われることを確保するための制度です。
これにより、消費税の計算がより透明性を持ち公正なものとなることが期待されています。
インボイス制度はいつから始まる?
インボイス制度は2023年10月から導入予定です。
この日から、事業者は新しいインボイス制度に基づいて消費税の計算や申告を行う必要があります。
そのために、適格請求書の発行と保存が必要になります。
インボイス発行事業者への登録方法
インボイス制度を利用するには、事業者は「インボイス発行事業者」として登録する必要があります。
登録は国税庁のウェブサイトで簡単に行うことができ、事業者は適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、これを基に消費税の計算や申告が可能となります。
登録は無料であり、インターネットから簡単に申請することができます。
その他の方法
インボイス発行事業者への登録は主にインターネットを通じて行われますが、インターネットが利用できない場合でも郵送による手続きが可能です。
具体的な手続きについては、国税庁のウェブサイトで詳細な案内が提供されています。
必要な書類をダウンロードし、申請書に必要事項を記入した後、最寄りの税務署宛に郵送しましょう。
申請が承認されると、事業者はインボイス発行事業者として登録され、適格請求書(インボイス)の発行が可能となります。
ただし、手続きには時間がかかる場合があるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
適格請求書(インボイス)とは
インボイスとは「適格請求書」を意味します。このインボイスは課税業者でなければ発行できません。
インボイス制度で使用される「インボイス」は適格請求書を意味し、輸入や輸出の貿易取引で必要となるインボイスとは異なります。
インボイス制度によって従来の請求書より記載しなければならない項目が増え、管理も厳しくなります。
適格請求書の必要記載項目
・売り手(受注者)と買い手(発注者)の事業者名と住所
・売り手(受注者)の事業者番号
・商品やサービスの内容、数量、価格
・取引に対する消費税の額
・請求書の発行日
これらの情報が全て記載されている請求書を「適格請求書」と呼び、仕入税額控除に使用することができます。(事業者番号とは、インボイス発行事業者として税務署に登録した際に発行される番号です。)
適格請求書は、デジタル(PDF)もしくは紙での保存が可能で保存期間は7年間と定められています。
こちらは、税務調査の際に必要となるためです。
適格請求書として扱える納品書の書き方
納品書を適格請求書として扱うには、以下の情報を納品書に全て記載する必要があります。
・売り手(納品者)の事業者名、住所、事業者番号
・買い手(納品先)の事業者名、住所
・商品やサービスの内容、数量、価格
・取引に対する消費税の額
・請求書の発行日(納品日)
これらの情報を納品書に記載することで、納品書が適格請求書として機能します。ただし、この方法を選択する場合でも、事業者は「インボイス発行事業者」として発行された事業者番号を忘れずに記載することが重要です。
また、納品書を適格請求書として使用する場合でも、保存期間は7年間と定められています。
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは
適格簡易請求書(または簡易インボイス)は、通常のインボイスと同様に消費税の計算に使用される特別な請求書ですが、必要な情報が少なくて済む書類を指します。
具体的には、売り手の事業者名と住所、事業者番号、そして請求書の発行日が必要です。
ただし、この特例は小規模な取引や一般消費者への販売など、不特定多数の者に対して販売等を行う事業者に限られます。
適格簡易請求書の交付ができる事業者
国税庁の資料によると以下の業種となります。
1.小売業
2.飲食店業
3.写真業
4.旅行業
5.タクシー業
6.駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
7.その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
参照:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
インボイス制度におけるレシート(領収書)の扱い
不特定多数の者に対して販売等を行う取引では、適格簡易請求書の発行が認められています。これに伴い、レジや券売機などで簡易インボイス対応の準備が進められています。
具体的には、2023年10月以降、従来のレシートに明記されている情報に加えて、インボイス発行事業者としての「事業者番号(登録番号)」が記載されるようになります。
これにより、小規模な取引や一般消費者への販売でも、消費税の計算や申告を正確に行うことが可能となります。発行した適格簡易請求書は、税務調査のために7年間保存する必要があります。
ただし、売上が1億円以下の中小企業については、2029年9月までの6年間は、1万円未満の課税仕入れ(経費等)に関して、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる支援措置が行われます。
インボイス制度の影響
インボイス制度の影響は、免税事業者か課税事業者かという点に加え、取引先がどちらになるのかでも異なります。
免税事業者への影響
現行個人事業主やフリーランスで課税売上が1000万円以下の場合は、免税となっています。
この免税事業者の中でも、例えば個人に対して販売したりサービスを提供している場合にはインボイスを発行する必要が無いため、インボイス制度開始後でも大きな影響がありません。
ただし、課税事業者へモノやサービスを売っている場合には、買い手側が消費税の仕入税額控除のためにインボイスを必要とします。
そうなると、仮にこれまで免税事業者だったとしても、インボイスを発行するために課税事業者になり消費税を納めなければならなくなります。
課税事業者からインボイスを要求される免税事業者は、インボイス制度によって課税事業者にならざるを得ない状況となります。
また、課税事業者としてインボイスを発行する「適格請求書発行事業者」は、返品や修正などによるインボイスの再発行に加え、写しを保存することが義務付けられます。
一人親方やフリーランスなどの個人事業主への影響
建設業やフリーランスのような個人事業主は、インボイス制度の導入により影響を受ける可能性があります。
インボイス制度の導入は任意ですが、登録しない場合は課税事業者との取引が減少する可能性があります。
特に、発注者(クライアント)が課税事業者の場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができないため、取引先として認めてもらえない場合があります。
また、免税事業者のまま取引を続ける場合は消費税相当額の値引きを求められる可能性もあります。
個人事業主はこれまで納付義務のなかった消費税を申告し課税事業者(インボイス発行事業者)になるか、免税事業者のままリスクを引き続き受けるかの二つの選択肢から選ばなければなりません。
個人事業主への影響は、施行日が近づくにつれてメディアでも広く取り上げられ議論されています。
個人事業主は、取引先とも相談しながら最善の選択をする必要があります。
課税事業者への影響
現行で課税事業者となっている企業は、インボイス制度開始後は取引先からインボイスを受け取らなければ仕入税額が控除されないため、できるだけ全取引先からインボイスを受けとる必要があります。
同時に自社が売り手となる取引では、インボイスを発行しなければなりません。
請求書の書式や税額の計算方法が変わることもあり、取引先や請求書の数が多い企業では大変な作業となります。
運送業界におけるインボイス制度の影響
インボイス制度は、運送業を営む個人事業主(軽貨物ドライバーなど)にも大きな影響を与えると考えられています。
国交省のデータによれば、軽貨物運送事業者は2021年度に20万9,250業者と過去10年間で3割以上増加しました。
このうち多くは個人事業主と考えられています。
運送業者の発注元(元請け・売り手)は課税事業者が多いため、インボイス制度の導入は運送業界に大きな影響を与えます。
免税事業者である運送業者(買い手・個人事業主)は、発注元からインボイスの交付を要求されても適格請求書を発行できないことから以下の影響が出ると予想されています。
・消費税額の値引きを求められる
・受注の優先順位が下がる
・契約が解除される
免税事業者から課税事業者への変更を求められたり、契約内容の見直しが必要となるケースもあると言えます。
卸売業におけるインボイス制度の影響
卸売業においても、課税事業者と免税事業者の取引に関する問題は存在しますが、「卸売市場特例」というインボイス制度の特例が使える場合があります。
参照:適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例の対象となる卸売市場について|農林水産省
対象となるのは、生鮮食品(野菜、果物、魚、肉など)、一般的な食料品、花き、農畜水産物など、卸売市場や農業協同組合を通じて取引される商品・生産物です。
農業者や生産者(免税事業者)は、農業協同組合や卸売市場を通じて委託販売する場合、特定の条件が満たされていればインボイスの発行が求められず、免税事業者として取引を継続することが可能です。
この特例は卸売市場における取引の特性を考慮しており、具体的な生産者を特定することが難しい場合や大量の商品を扱う場合など、インボイスの発行が困難となる状況に対応しています。
これにより、卸売市場を通じて商品を取引する事業者は、インボイス制度の導入による影響を最小限に抑えることができると言われています。
インボイス制度の経過措置とは
2023年10月から開始されるインボイス制度ですが、実は経過措置が設けられています。この経過措置とは、2023年10月から2029年10月までの6年間とされている移行措置です。
前半3年間は免税事業者からの仕入の80%、後半3年間は50%が控除されることになっています。
この6年間の経過措置が終了する2029年10月以降は、免税事業者からの仕入は控除されません。
知っておくべき緩和措置『2割特例』
2割特例は、消費税の納税額を計算する際に、預かり消費税から20%を控除できる制度です。具体的には、納税額が「預かり消費税 - (預かり消費税 × 80%)」で計算されます。この措置により、実質的に納税額を”預かり消費税の20%”に抑えることができます。
また複雑な計算や手続きを必要とせず、基本的に申告時に簡単に適用できる上、消費税の納税額が大幅に減少するため、小規模事業者の負担軽減につながります。
対象者
この特例の対象となるのは、インボイス制度が開始されたことを機に初めて課税事業者(インボイス発行事業者)になった事業者です。
特に免税事業者から切り替えた場合に適用されます。
注意点
- 一時的な措置であり、2023年10月1日~2026年(令和8年)9月30日までの3年間に限定されています。この期間が過ぎると、通常の税率が適用されるため、長期的な計画が必要です。
- 特例は条件を満たした事業者のみが利用できる制度です。たとえば、一定の売上げ(1,000万円)以上や他の課税選択をしている場合は適用外となります。
- 他の課税制度(例えば簡易課税制度)との選択を迫られる場合、どちらが最適か判断が難しい場面があります。
詳しくは、国税庁による「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」をご確認ください。
インボイス制度開始に向けてすべきこと
インボイス制度が開始される2023年10月までにすべきことをまとめると以下のようになります。
免税事業者
まず現在免税事業者である場合、インボイス制度開始に向けて2つの選択肢があります。一つはこのまま免税事業者としてやっていく選択肢、もう一つは課税事業者となる選択肢です。
インボイス制度開始後に免税事業者のままであっても影響が出ないのは、売上先もすべて免税事業者または一般消費者である場合です。
取引先が仕入額控除を受ける対象ならば、控除が受けられない免税事業者からは買いたくないとなるはずです。
このまま免税事業者としてやっていくのであれば必要な届け出はありません。
ただし先ほども経過措置のところでお伝えしたように、免税事業者でもインボイス制度開始後は一部消費税を納めなければならなくなることに変わりはありません。
帳簿の記載が複雑になるため、会計ソフトなどがインボイス制度に対応しているかどうか確認し、非対応なら対応したものに変更する必要があるでしょう。
もし、インボイス制度の開始に伴って課税事業者になることを選んだ場合は、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
通常免税事業者が課税事業者になるためには、税務署に「課税事業者選択届出書」を提出しなければならないのですが、インボイス制度開始に伴った適格請求書発行事業者の登録申請はこの選択届出書の提出が省略可能です。
2023年10月のインボイス制度開始時に適用を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請しなければなりません。
まだ迷っているという場合には、その後6年間の経過措置期間があるためあわてて登録申請する必要はなく、随時決定次第登録申請した日から適格請求書発行事業者になる方法もあります。
課税事業者
インボイス制度開始前から課税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。
そのほか請求書の形式変更など経理部門での対応が必要になります。
取引先が免税事業者か課税事業者かどうかを確認しての対応が必要となるものの、現在免税事業者である取引先に消費税分の値引きを持ちかけるなどの行為は、場合によって独占禁止法や下請法上の問題となることがあるため注意が必要です。
インボイス制度の問題点と対策
管理負担の増加
インボイス制度の導入により、事業者は適格請求書の発行と保存が必要となるので書類の管理や記録保持に関わる時間と労力が増える可能性があります。
このような課題に対しては、専用の会計ソフトやシステムを導入することで手作業での作成やファイリングにかかる手間を軽減し適格請求書の発行と管理を効率化することができます。
制度への理解不足
インボイス制度は新しい制度であり、専門的な知識が必要となります。
制度に関する理解が不十分な場合、誤った手続きを行う可能性があります。
このような課題に対しては、税務署や地方自治体が提供する情報や、勉強会・説明会・相談窓口などに足を運び制度の理解を深めましょう。
小規模事業者への影響
インボイス制度は、特に小規模な事業者にとっては負担となる可能性があります。
自身の事業規模や取引の内容に応じて、制度の適用を選択するかどうかを検討する必要があります。
状況に合わせた適切な判断をするために、専門家の助言を受けたり、クライアントとの協議を重ねておくことが大切です。
導入に伴う初期コスト
インボイス制度の導入には、新たなシステムの導入や専門家に依頼するための初期コストが発生します。
そのため施行前に情報収取をしたうえで予算計画を立て必要なコストを見積もりましょう。
また補助金や支援制度を活用できる場合もあるので、税務署や自治体へ相談してみるのも良いでしょう。
参照:インボイス制度への対応に 取り組む皆様へ 各種支援策のご案内|経済産業省
取引関係の変化
インボイス制度の導入により、取引関係に変化が生じる可能性があります。
免税事業者から課税事業者への変更が必要となる場合、取引先との契約内容の見直しや調整が必要になるかもしれません。
このような場合、取引先との密なコミュニケーションを図り、早めに契約内容の調整を行うことが重要です。
同様に、取引先も新制度への適応が必要となるため情報の共有や協力が望ましいです。
共に効果的な移行を進めるために、円滑なコミュニケーションを心掛けましょう。
インボイス制度に関するQ&A
インボイス制度の登録申請に必要な書類は何ですか?
インボイス制度の登録申請には、事業者の基本情報を記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書」が必要です。
これには、事業者の名前や住所、事業の内容、申告書を作成した日付などが含まれます。
参照:適格請求書発行事業者の登録申請書(ダウンロード)|国税庁
インボイス制度はWebで登録できますか?
インボイス制度の登録は、国税庁のe-Taxシステムを通じてオンラインで行うことができます。
海外在住フリーランスには影響あるの?
海外在住のフリーランスが日本の企業にサービスを提供する場合、インボイス制度は直接的な影響を与えないと考えられます。
このような取引は消費税の対象外とされているため、海外在住のフリーランスが日本の企業に対して発行する請求書には消費税は含まれません。したがって、インボイス制度が始まっても海外在住のフリーランスが日本の企業に対して発行する請求書には消費税が含まれないため、インボイス制度の適用外ということになります。
家賃など契約書に基づいた決済が行われる場合は?
賃借人が事業者であり、消費税の課税事業者である場合、賃貸人(家主)は新たに適格請求書登録番号や賃料に関する消費税率や消費税額を明記した通知書を発行する必要があります。
また、新しい賃貸契約を締結する際には賃貸人の名前と登録番号、賃借人の名前や取引の内容、税率ごとの合計対価額と適用税率、消費税額を契約書に明記する必要があります。
これにより、賃借人は仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス制度に対応しているキャムマックス

このように、インボイス制度がスタートすることで多くの企業が複雑な変更に対応していく必要が出てきました。
もしも、手書きで請求書や帳簿を作成している場合には、インボイス制度開始後はもちろんさらに大変な作業となるでしょう。
また、何らかのソフトを使用していた場合でも、インボイス制度に対応していないと移行作業から始めなければなりません。
その点キャムマックスならインボイス制度に対応した帳簿や請求書の作成が可能なので、管理が楽々です。
インボイス制度開始に伴う切り替え作業などに頭を悩ませている中小企業様におかれましては、ぜひ一度キャムマックスまでご相談ください。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。