RFIDとは?仕組みや特徴について解説!在庫管理等の活用例も
RFIDは、電波を用いてICタグの情報読み取りを行う技術です。
非接触で一括スキャンが可能になり、数百の商品を一瞬で正確に管理できます。また障害物越しや汚れたタグも読み取り可能一括で複数タグを読み込むことができるなど従来のバーコードと比較したメリットも多いことから、導入する企業が増えてきました。
本記事では、このRFIDの仕組みや魅力をご紹介しつつ、倉庫や店舗などの製造現場においてこの新たなソリューションが在庫管理にどのような変化をもたらすのかじっくり解説します。
目次
RFIDとは?バーコードを超える無線通信の革新

RFIDは「Radio Frequency IDentification」の頭文字をとった略語で、読み方は「アールエフアイディー」です。RFIDでは、商品情報が書き込まれたRFタグが自ら電波を発することができるため、非接触での読み取りが可能となります。
現在、ETCカードや交通系ICカード、無人レジなどモノにRFタグをつける活用例が中心です。今後は人につけることで移動データを収集することにも活用されると言われています。
RFIDの仕組み
RFIDは、RFタグとリーダ間で双方向にデータを送受信する仕組みによって成り立ちます。リーダ側から電波が発信されると、これに応じる形でRFタグからも電波が発信されます。その後、リーダによって読み取られた情報は、コンピュータに転送されます。
RFIDの特徴
RFIDが従来のバーコード読み取りシステムと異なる点を紹介します。最も大きな違いは、タグから電波が発信できるかどうかという点です。
従来は印刷されたバーコードを一つ一つバーコードリーダで読み込むという作業が必要でしたが、RFIDは一度に複数のタグから情報を読み取ることができるのです。
RFIDとNFCの違い
RFIDとNFC(Near Field Communication)は、どちらも無線通信技術ですが異なる目的で使われます。RFIDは一定の距離(数メートル以上)からの読み取りが可能で、物流管理や在庫管理など幅広い用途に使われます。
一方、NFCは近距離通信技術(数センチメートル以内)であり、スマートフォンやICカードなどのデバイス間の短距離通信に使われ、主に決済やデータの交換などに活用されています。
RFIDアンテナ
RFIDアンテナは、RFIDシステムで電波の送受信を担当する装置です。アンテナは、リーダー/ライターに組み込まれる場合やタグ内に内蔵される場合があります。
アンテナは、電波の伝送効率や通信範囲を最適化するために設計されており、RFIDシステムの性能に大きな影響を与えます。そのためアンテナの形状や配置は、具体的な使用環境やアプリケーションに合わせて調整されることがあります。
RFIDタグ
RFIDタグは、ICチップとアンテナで構成されるデバイスで情報の保存や非接触での読み書きが可能です。タグには個別の識別情報やデータが含まれており、リーダー/ライターとの通信を通じて情報をやり取りします。
RFIDタグはさまざまな形状やサイズで提供されており、使用する周波数帯やメモリ容量などによって異なる種類が存在します。
RFIDリーダー
RFIDリーダー(またはRFIDリーダライタ)は、RFIDタグとの通信に使われるデバイスであり、非接触でICタグの情報を読み取ったり書き換えたりする役割を担っています。
電磁波や電波を使用して通信を行うRFIDリーダーには、スマートフォンと連携するタイプや卓上に置くタイプや壁や天井に取り付けるタイプなどさまざまな種類があります。
RFIDプリンター
RFIDプリンターは、RFIDタグに情報を書き込むための特別なプリンターです。通常、ICタグやRFタグにデータや識別情報を印刷しそのタグを製品に貼り付けることができます。
これによって、商品管理や在庫管理などの目的で効率的にRFIDタグを作成することができます。
ICタグを活用した在庫管理方法
一般的に、「ICタグを活用した在庫管理」とは、RFID技術を用いた在庫管理システムを指します。これにより、在庫管理プロセスが効率化され、正確性が向上します。
手順① 各在庫品にRFIDプリンターを用いてICタグ(RFIDタグ)を取り付けます。
これには製品情報、ロット番号、製造日などが含まれることが多いです。
手順② RFIDリーダーを設置する。
ICタグの情報を読み取るために、在庫を管理する倉庫などにRFIDリーダーを設置します。
手順③ データの統合・管理
読み取ったデータはの在庫管理システムに送信され、リアルタイムでの在庫追跡と管理が可能になります。
RFID導入で在庫管理が変わる!そのメリットと強み・特徴について
| 項目 | バーコード | RFID |
|---|---|---|
| 読み取り方法 | 光学スキャン | 無線通信 |
| 読み取り距離 | 数センチメートル以内 | 数メートル以上 |
| 同時読み取り | 1つずつ | 複数同時に可能 |
| 読み取り速度 | 遅い(手動操作) | 速い(非接触で一括読み取り) |
| 耐久性 | 低い(紙などで損傷しやすい) | 高い(ICチップで頑丈) |
| データの再利用性 | 1回限り(使い捨て) | 繰り返し利用可能 |
| 導入コスト | 低コスト | 比較的高コスト |
このように、RFIDはタグを使った商品・在庫管理に画期的な進歩をもたらしました。
次に、RFID導入の具体的なメリットを見ていきます。
離れた場所からでも読み取れる
タイプにもよりますが、従来のバーコードリーダではバーコードとの距離が数mmから最長でも約80cm以上離れると読み取ることができません。一方、RFIDはタグからも電波が発信されるため、その通信距離は最長数10mと長距離に対応しています。
離れていても瞬時に読み取ることができるため、倉庫の高い場所にある在庫でも下ろさずに読み取ることができるでしょう。
障害物があっても読み取り可能
従来のバーコードであれば、商品についているタグを読み取るために該当の箱を探して開けるという作業が必要でした。RFIDの場合はタグが表面に無くても読み取り可能なため、わざわざ箱を開ける必要がありません。
汚れに強い
紙などに印刷されている線の幅を読み込む従来型バーコードの場合、線が消えていたり汚れているとデータを読み取ることができませんでした。
RFIDは、タグに含まれているICチップ内のデータを電波で読み取るため表面の汚れは関係ありません。
複数のタグを一括読み込み
RFIDであれば、RFタグの付いている複数商品を一度に全部読み込むことができます。一つ一つバーコードリーダで読み取っていた従来の作業時間と比較すると、大きな短縮となります。
データの書き込み・書き換えが可能
RFIDは、タグに含まれるデータを追加したり変更したりすることが可能です。従来のバーコードはデータ変更時は印刷し直す必要があるため、1回限りの使い捨てになってしまいます
一方で、RFタグの場合は何度も書き換えて使用することができるのが特徴です。
RFIDの種類

RFIDは、タグのバッテリー構造や周波数、通信方式によりいくつかの種類に分かれます。
タグのバッテリー構造による種類
RFタグはバッテリーがあるかないか、ある場合にはサイズなどで以下の3つに分類されます。
パッシブタグ
バッテリー不要で、リーダーから送られる電波エネルギーを利用して動作するタグです。コンパクトでコストが低く、一般的に広く使われています。
在庫管理や物流管理など、さまざまな用途で幅広く活用されています。
セミアクティブタグ
バッテリーを搭載した小型のタグで、リーダーからの電波エネルギーとバッテリーの組み合わせで動作します。特定の信号を受信するとアクティブタグとして機能し、入退室管理やタイム計測などに活用されます。
アクティブタグ
大型のバッテリーを備えており、自己の電力で通信を行います。長距離通信や高性能の読み取り能力を持ち、広範な追跡や位置情報の取得ができます。
コンテナや重機などの監視や追跡に広く活用されています。
周波数や通信方式による種類
RFIDでは、電波の送受信に使う周波数と通信方式では以下の4種類に分類されます。
LF帯
周波数が135KHz以下の電磁結合もしくは電磁誘導を利用したタイプで、車のスマートキーなどに利用されています。
HF帯
周波数が13.56MHzの電磁結合もしくは電磁誘導を利用したタイプで、交通系ICカードなどに利用されています。
UHF帯
周波数が433MHzもしくは860〜960MHzの電波を利用したタイプで、大規模な在庫管理などに利用されています。
マイクロ波帯
周波数が2.45GHzの電波を利用したタイプで、製造ラインなどで活用されています。
RFID導入コストと価格|導入にかかる費用とコスト削減方法について

RFIDリーダーやRFIDタグの価格についての考え方とポイント
RFIDシステムを導入するには、RFIDタグやリーダー・プリンター・周辺機器などを購入する必要があります。RFIDタグの価格は通常1枚あたり5~10円程度であり、バーコードと比較すると費用負担が高くなります(バーコードの場合は1枚あたり2~3円)。
RFIDタグの価格には、使用する周波数帯、容量、機能性などの要素が影響します。同様に、RFIDリーダーの価格も異なるため導入時には予算や要件に応じて適切な機器を選ぶことが重要です。
経済産業省が目指すRFIDタグの低価格化|導入普及への取り組みと目標
経済産業省はRFIDの普及を促進するために、RFIDタグの価格を1円以下にする取り組みを行っています。こちらの取り組みによって、RFIDの導入コストが削減され、さまざまな業界や企業での利用が促進されることが期待されています。
2025年までにコンビニ電子タグ1000億枚宣言
経済産業省は、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ニューデイズの各社と合意し、2025年までに全商品(推定1000億個/年)に電子タグを適用することを目指す「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を策定しました。この取り組みは、商品の個品管理を実現し、サプライチェーンの効率化と社会課題の解決を目指します。
・宣言内容
2025年までにコンビニ各社は全取扱商品に電子タグを適用し、商品の個品管理を実現します。また、電子タグから得られる情報の一部をサプライチェーン(製造者や販売業者)に提供することを検討します。また、電子タグの普及型単価が1円以下であること、RFIDで管理可能な環境を整備します。
・RFIDの利点と将来像
電子タグ(RFID)は、非接触で複数のタグを一括読取可能であり、商品の流れを自動的に把握し、流通システムのムダを特定できる効率化を提供。RFIDの導入により、欠陥品のトレーサビリティや細かな消費期限管理が可能になり、食品ロスの削減など様々な波及効果が期待されます。
引用:「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」を策定しました(一般社団法人日本加工食品卸協会)
リンクのPDF資料には、詳しい宣言内容のほか、課題や実現に向けたロードマップも記載されているのでぜひチェックしてみて下さい。
電子タグ(RFID)を活用した食品ロス削減に関する実証実験
経済産業省は、伊藤忠商事株式会社を委託事業者として、コンビニエンスストアでの食品ロス削減を目的としたRFIDを活用した実証実験を実施します。この実験は、消費期限が短い商品(弁当・おにぎりなど)の管理効率を向上させ、食品ロスを減少させることを目指しています。
【実証実験の内容】
- RFIDタグを消費期限の短い商品に付け、入荷検品時から販売までの流れを追跡。
- RFIDを読み取ることができるスマートシェルフを使い、在庫状況や消費期限をリアルタイムで自動管理。
- 消費期限が近い商品には、ポイント付与や直接値引きを行い、消費を促進。
【実験の期間と場所】
- 実証実験(1): 令和2年11月2日から令和2年11月30日まで、ファミリーマート 京王プレッソイン池袋店およびファミマ!! ThinkPark店で実施。
- 実証実験(2): 令和2年12月7日から令和2年12月28日まで、ポプラ 鬼子母神店および生活彩家 秋葉原駅前店で実施。
【実験の目的と期待される効果】
この実証実験を通じて、コンビニエンスストアの省力化と食品ロスの削減や廃棄率の低下を図り、サプライチェーンの効率化と生産性の向上を目指します。RFID技術を活用することで、消費期限が迫った商品の効果的な管理と販売促進が可能となり、全体的な運用コストの削減にも寄与することが期待されています。
RFIDの活用事例|在庫管理や物流の効率化事例を紹介

今RFIDは様々な業種や場面で活用されています。時間短縮、人員削減を中心とした業務改善の活用例を挙げてみます。
RFIDを活用した在庫管理システム
RFIDが使える在庫管理システムは、より効率的な在庫管理が可能となります。商品や資産にRFIDタグを取り付けてリーダーで情報を読み取ることによって、在庫の追跡や管理が自動化されます。
以下に、その利点をご紹介します。
【迅速な在庫管理】
RFIDタグは非接触で情報を読み取ることができるため、バーコードと比較して大量の商品を素早く処理することができます。これにより、在庫の棚卸しや商品の受け渡し作業の時間を大幅に短縮できます。
【高い正確性】
RFIDによる自動読み取りは、データが自動的に読み取られるため正確な在庫数や商品の位置情報を維持することができます。これにより、人為的なミスや目視による誤りを防ぐことができます。
【リアルタイムの可視化】
RFIDを用いた在庫管理システムでは、在庫の状況や移動履歴をリアルタイムで把握することができます。これにより、在庫不足や過剰商品の位置情報を容易に把握し、適切な補充や在庫調整が可能となります。
このようにRFIDを活用することで、在庫管理が迅速かつ正確に行われるため、効率的な業務運営が実現できます。
製造業・小売店などでの在庫管理作業
製造業や運輸業、小売業などでは、在庫管理や棚卸作業の効率化をどの企業も目指しています。具体的には、入出庫管理、ロケーション管理、持ち出し管理などの作業の削減です。下記の特徴が課題解決につながるかもしれません。
【自動化された受け渡し作業】
RFIDタグを搭載した商品やパレットは、リーダーによって自動的に識別され受け渡しの手続きを自動化できます。これにより、作業効率が向上しミスや遅延が減少します。
【倉庫内の追跡と位置情報】
RFIDタグを付けられた商品やパレットは、倉庫内での位置を正確に追跡することができます。これにより、在庫の配置やピッキング作業の最適化に役立ちます。
【在庫のリアルタイム表示】
RFIDによる在庫管理システムでは、倉庫内の在庫状況をリアルタイムで表示することができます。倉庫内の各商品や資産に付けられたRFIDタグは、リーダーによって読み取られ、在庫の数量や位置情報が即座にデータベースに反映されます。これにより、倉庫管理者や作業員は、PCやスマホなどを通じて、いつでも在庫の状況を把握できます。
RFIDを導入することで一括読み取りが可能となり、人的ミスを防ぐことができます。結果として、時間を節約するだけでなく、人的リソースも削減できるでしょう。
RFIDとバーコードによる在庫管理の違い
RFIDとバーコードは、在庫管理に使用される自動認識技術ですが、いくつかの違いがあります。
読み取り方法
バーコードは光を使って情報を読み取りますが、RFIDは無線通信を利用して非接触で情報を読み取ります。RFIDは複数のタグを同時に読み取ることができるため、スキャン作業が迅速です。
読み取り範囲
バーコードは近距離での読み取りに依存していますが、RFIDは無線通信を使用するため、遠距離からの読み取りが可能です。
データの容量
バーコードは数十桁の情報を表現できますが、RFIDはより多くのデータを格納できます。RFIDタグにはユニークな識別子や追加情報を含めることができます。
耐久性と再利用性
バーコードは紙やプラスチックで作られており、耐久性に限界があります。一方、RFIDタグは耐久性があり、繰り返し使用することができます。
自動化の度合い
RFIDはデータを自動的に読み取ることができるため、作業の自動化に適しています。バーコードは手動でスキャンする必要があるため、手作業が必要です。
工場での工程管理
製造業においてRFIDを導入することで、生産ライン上のアイテムや部品の管理を効率的に行うことができます。各工程に取り付けられたRFIDタグを使用して、生産工程の追跡と管理を効率化します。
工程ごとのタグはハンディターミナルなどリーダーによって読み取られ、作業者はリアルタイムで工程の進捗状況や在庫の確認ができます。作業効率の向上や生産ラインのスムーズな運営、不良品の早期発見と追跡、在庫の正確な管理などが期待されます。
社内や事務所での資産管理
RFIDは資産管理においても有効であり、位置情報の取得などができるので備品や書類、メディアなどの持ち出しによるセキュリティの漏洩問題を防ぐのに役立ちます。
たとえば会社内の機器や設備にRFIDタグを取り付けることで、リアルタイムでその位置や状態を把握することができます。また、資産の貸出や返却の管理も容易になります。RFIDを活用することで、資産の盗難や紛失を防止し、効率的な資産管理を実現できます。
備品管理や棚卸しにもRFIDを活用できる
RFIDタグには備品の詳細情報(購入日、保証期間、メンテナンス履歴など)を記録し管理することが可能です。生産業や建設業であれば工具、作業着、機械、機材、什器など。また医療機関であれば、病院やクリニックで使用される医療機器や器具。この他にも、コンピューター、サーバー、高価な電子機器などにRFIDタグを付けておけば常時管理が行え、棚卸にも迅速に対応できます。
POSレジによる会計
商品点数が多い場合、レジの作業には時間がかかりますがRFIDの導入によりこの時間を短縮することができます。これにより、以前は会計待ちの列が解消され、さらには無人レジへの変更も可能になります。
またRFIDタグを商品に取り付けることで、レジスタッフは商品をスキャンする代わりにタグを読み取るだけで商品情報を取得できます。
これにより、商品のチェックアウト(会計)もスムーズに行え、時間を短縮することができます。また在庫管理との連携により、在庫切れを回避し顧客の満足度を向上させることも可能です。
ユニクロにおけるRFIDの活用事例
ユニクロはRFIDを大規模導入している企業の一つです。
RFIDは商品の識別や在庫管理に活用されており、特にユニクロではセルフレジシステムにおいてその利点が活かされています。顧客が商品を購入する際、RFIDタグが商品から無線通信によって読み取られ、自動的に会計処理が行われます。このシステムにより、従来のバーコード方式と比べてスムーズな会計が可能となり待ち時間の短縮やレジの人材をなくすことが可能になりました。
さらに、RFIDを活用した在庫管理により、正確かつリアルタイムな在庫情報を把握することができます。RFIDタグによって商品の識別が行われ、在庫の入出庫や棚卸作業が効率化されます。これにより、商品の欠品や過剰在庫のリスクを最小限に抑えることができ、効率的な在庫管理と商品供給を実現しています。
ユニクロの事例を通じて、RFIDが小売業において効果的なツールとして認識されました。
RFIDを導入して在庫管理をDXを加速

様々な業務を改善し、効率化させることができるRFIDを導入することはDX化を一気に進めることにつながります。
RFIDに適している環境
様々な障害にも耐えられるRFIDですが、それでも基本は屋内で、紫外線や雨、埃などの外的要因に影響されにくい環境が望ましいです。また、電波の広さや半径を考慮し、出来る限り障害物がない影響を準備するとより良いかと思います。
RFIDで在庫管理をする際の注意点
RFIDは在庫管理の手法として非常に有効です。しかし、実際に使ってみると、環境や対象が在庫管理に向いていないこともあります。このような事態を避けるためには、再度RFIDの特徴を理解した上で、自社の倉庫環境が適しているのか、コストよりも適合性を見極める必要があります。場合によっては、高度なRFIDよりも、地味なシールの方が有利な場合もあります。
RFIDで在庫管理が出来ない場合
キャムマックスでは、RFIDの活用事例以外にも在庫管理をはじめとするあらゆる業務を一元管理する機能があります。
RFIDを活かして在庫管理がしたい! 予算がないのでとりあえずハンディだけで倉庫・在庫管理をしたい! どちらの場合でもキャムマックスでは業務をサポートする機能が備わっております。
在庫管理でお悩みでしたらお気軽にお問合せください。
クラウドERPシステム『キャムマックス』とRFIDで実現する在庫管理の効率化

キャムマックスは、RFIDにも対応しているクラウドERPシステムです。在庫管理や棚卸などがスムーズに行え、倉庫管理・販売管理・財務会計まで一元管理ができます。
リアルタイムで在庫数や売上も把握できるため、特に取り扱い商材の多い製造業や小売業の企業様にはおすすめです。
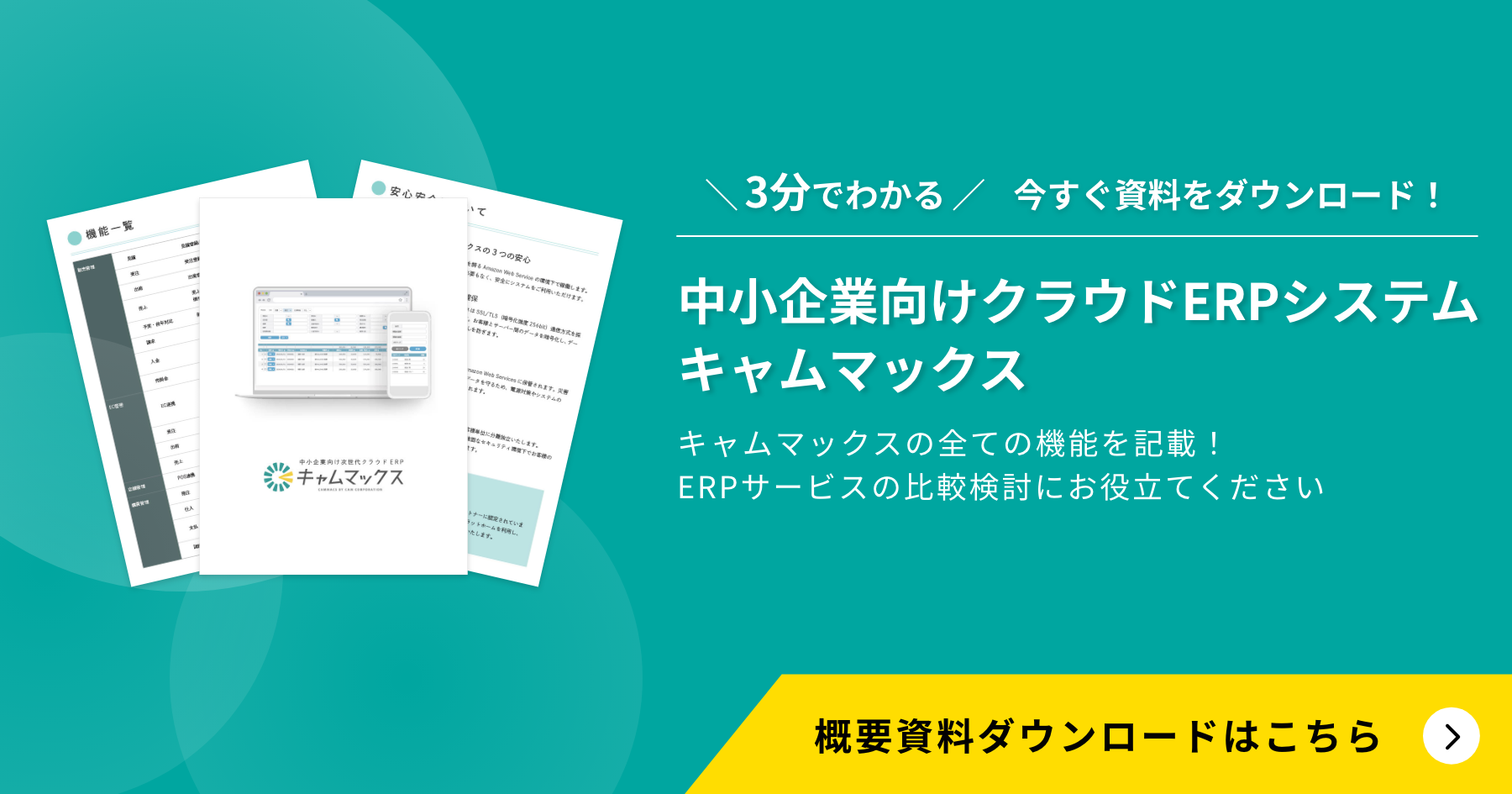
FAQ(よくある質問)
Q1. RFID技術とはどのようなもので、どのように利用されていますか?
A:RFID(Radio Frequency Identification)は無線通信を利用してICタグの情報を読み取る技術です。タグには商品情報や識別番号が記録されており、リーダーによって非接触でデータの取得が可能です。RFIDは在庫管理や物流管理、無人レジ、ETCなど幅広い分野で利用されています。
Q2. RFIDを導入することで、どのようなメリットがありますか?
A:主なメリットには『複数のタグを一括で非接触で読み取れる』『長距離でも情報を取得できる』『障害物越しでも読み取り可能』が挙げられます。また、データの書き換えが可能なためタグを再利用できる点も優れています。
Q3. RFIDとNFCの違いは何ですか?
A:RFIDは数メートル以上の距離で通信が可能な無線技術で、物流や在庫管理に広く利用されています。一方、NFC(Near Field Communication)は数センチメートルの近距離で通信する技術で、スマートフォンやICカードを使った決済やデータの交換に使用されます。
Q4. RFIDタグにはどのような種類がありますか
A:タグは、バッテリーの有無や通信方式によっていくつかの種類に分かれます。主に、電池を使わずリーダーの電波を利用して動作するパッシブタグ、小型のバッテリーを搭載したセミアクティブタグ、そして長距離通信や高性能な読み取りが可能なアクティブタグの3種類があります。
Q5. RFIDシステムを導入するには、どのくらいのコストがかかりますか?
A:導入コストは、使用するタグやリーダー、システムの規模によって異なります。一般的なRFIDタグは1枚あたり5~10円程度ですが、大量に使用する場合や特定の用途に適した高性能なタグはさらに高価になります。経済産業省ではRFIDの普及に向けて、タグの価格を1円以下に抑える取り組みを進めています。
Q6. RFIDを使った在庫管理の手順と仕組みはどうなっていますか?
A:各商品にRFIDタグを取り付けて、リーダーを通して非接触でタグ情報を読み取ります。その情報は在庫管理システムに送信され、リアルタイムで在庫数や商品の位置を把握します。この方法により手動での作業が減り、データ入力時間の短縮と正確な商品管理が可能になります。
Q7. RFIDを導入する際に、デメリットや注意点はありますか?
A:RFIDの導入には初期コストが比較的高いというデメリットがあります。また、環境によっては電波干渉やリーダーの設置場所が制約となる場合があり、すべての場所や用途で適用できるわけではありません。
Q8. RFIDはどのような業界や場面で利用されていますか?
A:製造業や小売業では在庫管理や物流管理に広く使われています。その他にも、医療機関における機器管理や建設現場での資材管理、コンビニやスーパーでの無人レジシステムなど、RFIDの適用範囲は非常に広がっています。