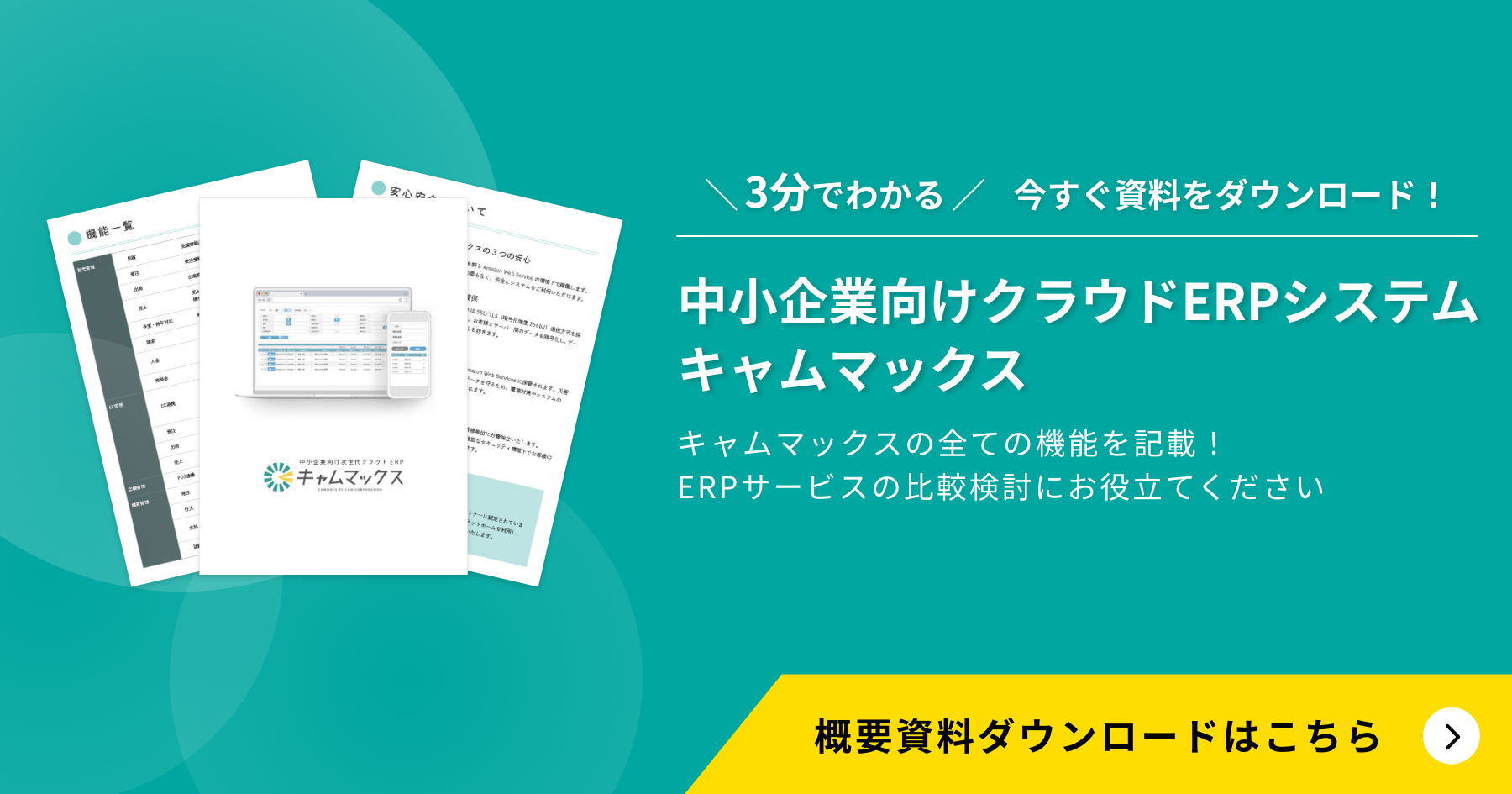「なんとなく導入」は危険!クラウドERPの導入を失敗させないためのポイントとは?
クラウドERPは、今や企業の経営戦略に欠かせない存在となりつつあります。業務の効率化やデータの一元管理、リアルタイムな情報共有など、多くのメリットがある一方で、「なんとなく導入した結果、うまく機能しなかった…」という失敗も少なくありません。
そのため、導入を検討している企業の中には、「自社に本当に合うのか」「失敗したらどうしよう」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、クラウドERPの導入で実際に起きた失敗事例を紹介しながら、その原因と対策についてわかりやすく解説していきます。
導入にあたって押さえておくべきポイントを知ることで、自社に最適な選択ができるはずです。クラウドERPを導入して経営基盤を強化するためにも、まずは“失敗しないための視点”を身につけていきましょう。
目次
ERPシステムの目的と利点について
ERP(Enterprise Resource Planning)システムは、企業のさまざまな業務プロセスを統合し一元化することが可能なシステムです。
以下では、具体的な例を挙げながらERPシステムの目的と利点を説明します。
業務プロセスの統合
たとえば、製造業の企業がERPシステムを導入すると、製品の生産管理から入出荷管理、販売管理、在庫管理、財務会計までの全てのプロセスが一元化され、より効果的な業務運営が可能となります。
たとえば、生産部門ではリアルタイムな在庫情報を把握し必要な部品の発注をスムーズに行うことができたり、在庫管理もリアルタイムで在庫数を確認できたり追跡、在庫過剰や在庫切れを防ぐ自動発注機能などがあります。
また、販売部門では最新の在庫情報に基づいて顧客に正確な納期を伝えることができますし、様々な販売チャネルがあっても売上を一つの画面でリアルタイムで確認することができます。
経理部門では手動で売上データを入力し請求書を作成する必要がなくなります。
ERPシステムを導入することで、これらの業務を効率化・自動化することができます。
リアルタイムの情報共有
ERPシステムの導入により、全社員はリアルタイムで最新の情報を簡単に把握できます。
たとえば、営業担当者が顧客からの注文をシステムに入力すると、その情報はすぐに生産部門や物流部門と共有され、スムーズな対応が可能となります。
意思決定の改善
ERPシステムの導入により、正確かつ迅速なデータを提供することで、経営陣は迅速かつ正確な意思決定を行えます。
販売データや在庫データ、財務データなどを活用して新製品の開発やマーケティング戦略や予算計画などの立案が可能となります。
よくあるクラウドERPシステムの導入の失敗事例

ERP導入で多くの企業が直面する失敗の要因を整理し、共通する落とし穴を明らかにします。
ERPは、企業の業務全体を統合的に管理し、生産性や可視性を向上させるツールとして非常に有効ですが、現実には導入の失敗が後を絶ちません。これにはいくつかの典型的な原因があります。
目的やゴールが曖昧なまま導入が始まる
ERP導入の根本的な失敗要因のひとつは、「なぜ導入するのか」が社内で共有されていないことです。経営層が“DX”という言葉だけで導入を急ぎ、現場と目指す成果の認識が食い違ったまま進行すると、実装後に「想像していた運用と違う」という事態に陥ります。
例えば「在庫の見える化」が目的なのに、それに必要なマスタ設計や運用設計が検討されていなかった場合、目標は達成されません。目的を数値化し、社内で共通認識として持つことが極めて重要です。
現場との乖離が大きく、業務フローに合わない
ERPは現場で使われるものであるにもかかわらず、導入設計段階で現場の意見が反映されていないことが多々あります。現場では「従来の方法の方が早い」と感じる場面も多く、結果的に新システムが使われなくなるというケースもあります。
また、現場が長年独自に工夫してきたプロセスを無視して一方的にシステムに置き換えると、モチベーション低下や非効率の温床になります。ERP導入は現場ヒアリングを通じて業務フローを正しく把握し、それに合わせた設計が求められます。
ERP導入がゴールになってしまっている
ERP導入プロジェクトはしばしば「導入完了=ゴール」と見なされがちですが、それは大きな誤解です。導入後に定着させ、運用改善を繰り返して初めて効果が生まれます。
マニュアルだけが配られて研修が不十分だったり、導入後のサポート体制が整っていなかったりすると、現場はすぐに旧システムやExcelに戻ってしまいます。システムの活用を習慣化させるには、現場の変化に寄り添った支援とPDCAサイクルの実行が不可欠です。
過度なカスタマイズによる運用コストの増大
「うちの業務には標準機能では対応できない」と、最初からカスタマイズを前提にERPを導入する企業もありますが、これは危険な判断です。
初期はうまくいっても、将来のバージョンアップや機能追加に支障が出たり、技術者が限られて保守が困難になるケースが多いからです。カスタマイズの負担は中長期的なコストの肥大化につながり、結果的にシステム全体の更新が難しくなります。
なるべく標準機能に業務を合わせる「フィット&ギャップ分析」を行い、最小限のカスタマイズで済ませることが重要です。
ERP導入に失敗しないための準備とは?
入前に検討すべきポイントと、社内でやっておくべき準備作業について解説します。
ERP導入の成功は、導入そのものではなく事前準備の質に大きく左右されます。とくに中小企業では、限られたリソースで最大の効果を得るために「準備段階」での判断と行動が極めて重要です。
業務プロセスを棚卸しし、現状課題を明確化する
ERP導入の第一歩は、自社の業務を細かく可視化することです。どの業務にどれだけの時間がかかっているのか、どこで属人化しているのか、ミスが発生している箇所はどこかなどを、ヒアリングと業務フロー図で整理します。この棚卸しによって、ERPに求める機能や改善対象がはっきりし、要件定義の質が格段に上がります。
ERP導入の目的とKPIを明確に定義する
「売上を伸ばしたい」「在庫を最適化したい」など、ERPに期待する成果は明文化し、できる限り数値目標(KPI)として設定することが望ましいです。KPIが明確であれば、ベンダーとのやり取りや社内調整もブレなく進められ、成果検証もしやすくなります。
社内メンバーのITリテラシーを確認する
ERPを運用するのはシステム担当者だけではありません。日々の入力・参照・承認などの操作を行う現場メンバーのITリテラシーが一定以上でないと、導入後に混乱が生じます。
Excelに慣れていない人が多い部署では、ERP操作に対する心理的ハードルも高く、習熟に時間がかかるため導入前に簡易トレーニングやデモ環境を活用する準備が重要です。
要件定義の段階で現場の声を取り入れる
ERP導入でありがちな失敗は、システム部門や経営層だけで要件定義を進めてしまうことです。
現場で実際に操作する人の声を反映しないと、使いにくいUIや非効率な運用になりがちです。導入プロジェクトには、必ず現場代表者を巻き込み、意見を取り入れる「参加型」の進め方が成功への鍵です。
クラウドERPの導入を失敗させないためのつのポイント

クラウドERPの導入において最も重要なのは、製品そのものよりも社内の体制づくりと導入プロセスの進め方です。
ここでは、中小企業がクラウドERP導入を成功に導くために整えておくべき社内側のポイントを4つ紹介します。
経営層のコミットメントを明確にする
ERP導入は全社的な変革を伴うプロジェクトです。
経営層が「導入の目的」「期待する成果」「予算配分」などを明確に示し、積極的に関与しなければ、現場の優先順位が下がりプロジェクトは形骸化します。現場任せではなく、トップダウンで推進力を持たせる姿勢が成功には欠かせません。
部門横断型のプロジェクトチームを編成する
ERPは部署をまたいで情報と業務を統合するため、1部門の判断だけで要件を決めると機能不全に陥ります。
営業、経理、在庫管理、総務など関係部門から担当者を集めたプロジェクトチームを編成し、互いの業務内容と課題を共有したうえで導入要件を整理しましょう。
各部門の代表がプロジェクトに関与することで、社内全体の理解と協力が得られやすくなります。
現場への情報共有と巻き込みを早期から行う
現場の協力がなければERPは「入れて終わり」になります。操作説明会やデモンストレーション、試用環境の提供を通じて、導入前から現場の関心と理解を高めていくことが重要です。
また、現場スタッフが「自分たちもプロジェクトに関わっている」と感じられるように、意見収集や小さな成功体験を積ませる工夫が必要です。
導入後の定着フェーズを計画に含める
多くのERP導入失敗例は、運用開始後のサポートが不十分であることに起因します。
導入が完了しても、操作に慣れず離脱する社員が出たり、旧来の業務に戻ってしまったりすることがあります。そのため、稼働後3ヶ月〜半年を「定着フェーズ」として設け、マニュアル整備やQ&A対応、運用フローの微調整などを継続的に行う体制を作っておくべきです。
クラウドERP導入の成功事例
【株式会社ビッグウイング】受注・出荷管理機能が充実している基幹システム・ERPへのリプレイス
株式会社ビッグウイングは、海外のアウトドア用品の販売や独自ブランドの企画、小売店や問屋への卸売、自社オンラインストアでの販売などを行っています。
会社の成長に伴い、特定の部署の従業員離職率が高くなる課題が浮上しました。原因として、増加する受注や出荷管理業務の負担が大きいことが判明しました。このため、業務フローの見直しと同時に、受注・出荷管理機能が充実している基幹システム・ERPへの刷新を行いました。
そこでクラウドERPシステム「キャムマックス」を導入したことで、受注から出荷指示までの業務負担が一部軽減され、誤出荷の削減にも成功しました。
また、棚卸業務の時間が短縮され、ECと倉庫管理システムとの連携により重複する入力業務についても改善されました。
詳しくは下記ページをチェック
https://www.cammacs.jp/case/bigwing/
【株式会社八天堂】EC事業において複数チャネルの管理を一元化し、業務効率を向上
株式会社八天堂は和菓子店として創業し、その後「くりーむパン」の大ヒットにより全国展開を果たしました。
さらにシンガポール、香港、東南アジア、カナダのトロントなど海外にも進出し、冷凍パンを通販で配送するスタイルを確立し、EC事業も大いに発展しました。その一方で、販売管理業務がシステム化されておらず、自社ECや楽天、Amazon、Yahoo!などの各管理画面から注文確認などの業務を行っており、受注が増えるにつれて業務の手間も増えてしまっていました。
そのため、クラウドERPシステム「キャムマックス」を導入し、複数の販売チャネルを一元化。業務効率を向上させることにしました。
ERPシステムの導入により、各サイトの管理画面の操作方法を覚える必要がなくなり、統一された作業手順で全てのサイトを管理することができるように改善され、その結果業務が特定の個人に依存してしまう問題も解消することができました。
詳しくは下記ページをチェック
https://www.cammacs.jp/case/hattendo/
【株式会社ガリレオ】販売管理や入出庫管理などの業務改善・DX化に成功
株式会社ガリレオは、ネットワークカメラシステムなどの防犯カメラ事業を全国の企業に展開しています。
最近では、防犯意識の高まりや映像解析の需要の増加により、企業が防犯設備の導入を希望するケースが増えています。
これにより、お問い合わせが電話やECから増加し社内の忙しさが増したことから、システムや業務フローの見直しを検討するに至りました。
その結果、販売管理や入出庫管理などの業務改善とDX化を目指すために、弊社のクラウドERPシステム「キャムマックス」を導入しました。
これにより、従来のExcelとシステムの併用から一元管理への移行が実現しました。二重入力や正確なデータの把握に関する問題が解消され、
また、一部の業務が特定の個人に依存していた問題も解決し、アナログ管理による工数削減にも貢献しました。
具体的には、見積書作成機能を活用し、クライアントに対して複数の見積もりを作成しデータ化できるようになりました。
これにより、提案までのプロセスがスムーズになりました。また、社内の在庫状況や売上状況まで把握できるようになったことも良かった点として挙げていただいております。
詳しくは下記ページをチェック
https://www.cammacs.jp/case/galileo/
どのERPか決められないなら「キャムマックス」がオススメ!

会社にERPシステムを導入したいが「結局どの製品が良いかわからない」「まずは気軽に導入できるERPはどれ?」などお悩みになられている方はクラウドERP「キャムマックス」がおすすめです。
主な機能として、在庫管理・販売管理・購買管理・財務会計といった基本機能に加え、生産管理やweb-EDI、他システムとのAPI連携も可能です。さらに、ノンカスタマイズで利用できるパッケージ型なのですぐにでも利用が可能です。
【関連記事】
キャムマックスが調べた「社内へのシステム導入で失敗したことがありますか?」調査
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。